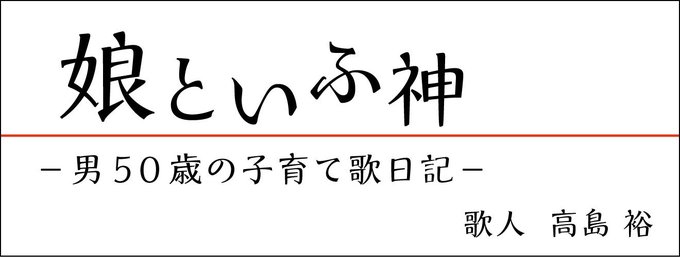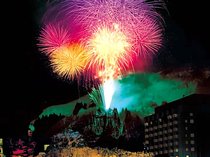産後一ヶ月を過ぎて、お宮参りを済ませ、母や姉夫婦に娘を会わせることができた。それから後は、少しずつ、娘をベビーカーに乗せて外へ連れ出すようになった。外気に当てて皮膚を鍛えるとともに、空や木々や草花や鳥たちを見せて、これから生きてゆく世界の彩りを感じさせたいと思った。
私たち新米母・新米父の悪戦苦闘は、日夜続いた。とくにこの時期大変だったのは、娘の「ミルク嫌い」だった。母乳を受けつけずにミルクばかり飲んで育ったらしい私とは逆に、娘はこの頃からミルクを飲ませようとしてもそっぽを向き、母乳ばかりを求めるようになった。その子その子の性向なのでやむをえないが、母親の負担と、母乳を飲み尽くした時の栄養の確保の点が心配だ。ある時、歌友で子育ての先輩である黒瀬珂瀾にこのことを話すと、「心配ありませんよ。すごくお腹が空いたらゴクゴク飲みますから」と笑っていた。実際その通りだったが、この後しばらく、私たちは娘の「ミルク嫌い」に悩まされ続けた。
そんな中で娘は順調に成長してゆく。「アーゥ」などと発声したり、笑ったり、手足をさかんに動かしたりするようになった。そして、生後三ヶ月が近づくころ、首がすわった。
首がすわらない間、私はひとりで娘をお風呂に入れることができなかった。何度か挑戦したが、生来不器用なのと不慣れで気後れしたりするせいで、娘の頭部が不安定になって危なっかしかった。他のことならともかく、娘の安全に関わることで失敗はあってはならない。私は、自分の無能力を認めて、沐浴は妻と、妻のお母さんに委ねた。子どもをお風呂に入れるのは、一般に父親の役割とされている。それができないことが寂しく、情けなかった。
けれども、ようやく首がすわって、念願の「子どもをお風呂に入れる」ができるようになった。それまではエア式のベビーバスを使っていたが、これからは大人と同じ浴槽に入れる。まずはわたしが洗い場で自分の体を洗う。衛生上の配慮だ。それから、妻に服を脱がせてもらった娘を抱き取る。浴槽には四十度より少し低いくらいの湯が張ってあり、洗面器にその湯を取って、大きめのプラコップで娘の体にかける。ベビー用のシャンプー、ボディーソープを手に取って、全身を優しく洗う。娘が泡の付いた手で目をこすったりするので、手は素早く洗って流す。耳にお湯が入らないように、内側に曲げるようにする。顔は濡らしたガーゼのハンカチでそっと拭く。最後に抱えて一緒に浴槽に入る。誤っておぼれないように、娘の体をしっかり抱える。怖い思いをさせて、お風呂を怖れるようになっては大変だ。乳児の皮膚はデリケートなので、お湯に浸かるのは短時間で切り上げる。バスタオルを手に広げた妻に、そっと娘を渡す。
妻は、早く自宅での三人の生活を始めたいとの思いから、時々自宅に娘を連れてきて徐々に慣らしていった。そして、百日のお食い初めを期して、実家を出て自宅での生活を始めた。私は、これまで生活丸ごとお世話になった妻のご両親に、心からのお礼を言った。
百日の空晴れわたり子のいのちもののいのちが夏へと迸(はし)る

◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。