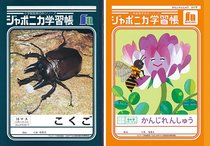今回のテーマは、農地(田、畑)です。自分で持っている農地に建物を建てたい、また親所有の農地に家を建てたい・・・という相談は、富山ならではかもしれませんが、多数いただきます。
農地を持っていないから関係ないと思われる方も、もしかしたら親せき又は近隣の方が持っていて、安く譲ってもらえるかもしれませんので、ご一読いただければと思います。
農地は国の財産 利用には規制あり
使用していない農地があるなら、自分で、または誰かに譲って宅地にしようと考えるのは自然な流れだと思います。そして、自分が所有しているのだから、どんな使い方をしてもよいのでは?と思うかもしれませんが、農地は国の大切な資源(財産)と考えられています。
なので、自分(又は親)の所有であったとしても、農地法や都市計画法などの法律で利用に規制がされています。ご相談を受けて「まさか親所有の農地に家が建てられないとは思わなかった」「手続きに、こんなにもお金と時間がかかるとは思わなかった」という声を、これまでたくさん聞いてきました。それらを踏まえて注意点を説明したいと思います。
区域による注意点
まず、日本の土地は大ざっぱに、市街化区域と市街化調整区域、その他に分かれることを覚えておきましょう。
使用する農地の面積が通常の大きさ(1000平方メートル以内)であれば、届出だけで農地を宅地に変えることができます。お役所から「受理証明書」が発行されます。
県としては市街化を抑制したい地域(農地を残していきたい→建物を建てたくない)場所なので、建築への難易度は高くなります。
手続きとしては、農業委員会への許可申請が必要です。その地域が「農用地区域」に該当すれば「農振除外」という手続きも必要です。「除外したい農地以外に代替すべき土地がないこと」などの要件があり、これらを文章化して県に提出します。それでも、農地転用の許可が出るとは限りません。「立地基準」という別の規制もあり、こちらもクリアしなければいけません。
もし市街化区域にある農地を安く譲ってもらえるのであれば、土地取得費用がかなり抑えられる可能性があります。
一方、市街化調整区域の農地は、市街化地域の農地よりもさらに土地が安くなる傾向がありますが、ご紹介した注意点を踏まえ、再度検討が必要かもしれません。市街化調整区域の手続きでは、申請から許可がおりるまで、場所によっては1年程度かかるケースもあります。
来年、消費税が10%に上がる可能性があり、建築を予定されている方は、早めの手続きをおすすめします。また 農地は、様々な法律の制限を受けますので、我々専門家にご相談いただければと思います。

猪島 隆雄
(いのしま・たかお)
司法書士法人谷道事務所 富山店の店長。相続、贈与、売買等を中心に、富山県全域において相談や登記手続きを行っている。司法書士、土地家屋調査士、行政書士。