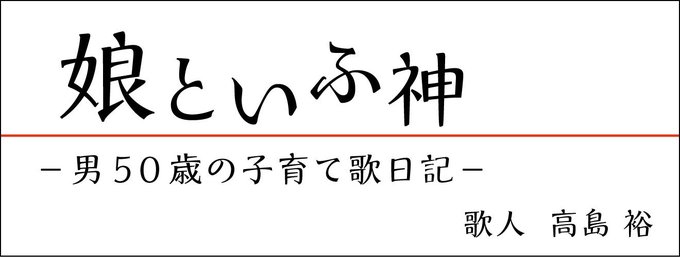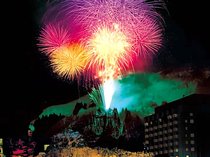三月一日は、穏やかな日差しが春の訪れを感じさせる、心地良い日和だった。昼休み、自宅に忘れ物をして取りに帰る途中、里帰りしている妻から電話が入った。前駆陣痛に続いて、「おしるし」と呼ばれる産前の出血があったという。予定日は三日後。もういつ産まれてもおかしくない。もちろんお産には立ち会うつもりなので、職場の人たちには状況を伝えておく。
翌三月二日。早朝五時に妻から電話。三時頃から痛みがきつくなってきたので、これから病院に向かうとのこと。続いて七時過ぎ、出勤の準備をしていると、妻のお母さんから電話が入る。陣痛は始まっているけれども、まだすぐに産まれる状態ではないので、いったん帰宅するように言われたとのこと。妻は、しんどくてもう電話には出られない。
続いて勤務中の午前十一時頃、再びお母さんから電話。もう一度診てもらった結果、入院が決まったとのことだった。すぐに職場を調整、上司にも連絡して、妻のいる病院に向かう。
昨日とは打って変わって雨が降りこめる中、熱に浮かされたような感覚で、高速道路を走る。実際には、この時は何も考えていなかった。ただ、早く妻のもとへ駆けつけることだけを思っていた。だが、そうでありながら、心の底で何となくもやもやしていたものを、今なら言葉にできる。

この時、妻は未知の苦痛と、言い知れぬ不安の中に放り込まれていた。それなのに私の方は、身体に何の変化もなく、いつも通りに出勤して仕事をしている。父親と母親。親となることに変わりないはずなのに、妻ひとりに産みの苦しみを負わせ、自分はいつも通りに平然としている。その罪責感が心の底に淀んでいた。こんなことを言うと、人に笑われるかも知れない。太古の昔から、父親とはそういうものだ、父親にはまた別の役割があるのだ、と。だが、そういう「常識」に凭(もた)れ、甘えていると、何か大切なものを取り逃がしてしまうような気がした。
病院に着くと、体温等チェックした上で、陣痛室に通された。妻は、痛みに耐えて横たわっている。陣痛は7、8分おきにやってくる。妻に寄り添っていると、ややあって、遠くの分娩室から、激しいいきみの声が聞こえてきた。妻は不安そうにそれを聞いていたが、いきみが産声に変わったとき、涙ぐんでいた。
陣痛室の昼の窓よりショベルカーの肘の部分が折々見ゆる
妻は、苦しくて病院食もほとんど食べられない。深夜になって、お腹の子の心拍数がひどく上がる。知らぬ間に破水していたとのことだが、子宮口が半分も開いておらず、なかなかお産が進まない。担当のドクターの決断で、妻の体力を養うため、いったん陣痛を抑える処置をして、休むことにした。付き添っている私と、妻のお母さんも、引き上げて、妻の実家で休むことになった。
日付は三月三日に替わった。

◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆
1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。