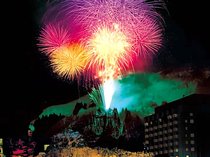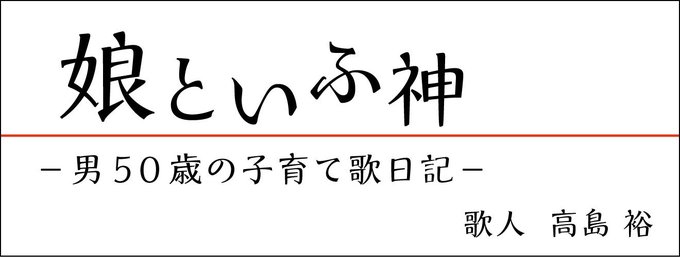
安産祈願を終えて数日後、生まれてくる娘の名前を「琳(りん)」と決めた。「琳」の字には、「美しい玉」「玉が触れて鳴る音」という意味がある。佳(よ)い字だ。生まれてくる娘への願いそのもののようだ。画数とか占いとかいったことは、まったく考えなかった。
秋から冬にかけて、妻のお腹はだんだん大きくなり、張りを訴えるようになった。ときどき胎動を感じることもあるようだ。それとともに、ひどくお腹が空くようで、妻の食事の量がぐっと増えた。お腹の子に栄養を送っているのだから当然で、しっかり食べてほしいと思ったが、困ったことに、血糖値が跳ね上がって、食事制限しなければならなくなった。妊娠中だけ血糖値が上がることはよくあるそうで、妊娠糖尿病と呼ばれている。出産とともに正常に復するとのことだが、お腹が空くのに厳しくカロリー制限され、日に何度も自分で血糖値を計測している姿は、とても辛そうだった。
年が明けて、予定日まで二ヶ月を切った頃、妻は実家に里帰りした。地元で産むか、里帰りして産むか、ずいぶん前から話し合い、迷った。地元で産みたい気持ちはあったが、私の父はすでに亡く、母は高齢で認知症を患い、グループホームで暮らしている。つまり、地元では、祖父母の援助は望めない。
自宅から妻の実家までは、高速道路を使って、車で一時間ほどの距離だ。そこには、妻のご両親と弟がいる。さまざま考えたが、やはり、生まれてくる子と妻にとって、より安心できる環境であることが何より大事だと思い、里帰り出産を選んだ。まだ里帰りするかどうか決めかねていた頃、ご両親にちらっと話をしたところ、ベビー用品を買って心待ちにしておられる様子だった。そういう気持ちでいてくださることが、何より心強く、安心できた。しばらくの間、私は週末ごとに妻の実家に寄せてもらう生活となる。
しかし妻は、その先のことを考えて不安がった。地元の保育所には生後半年で入れるように手続きしてあったが、それまでの間のことが心配なのだ。当然、私は仕事があるので、日中家を空けざるを得ない。育児を経験した先輩は、母親ひとりが家にこもりきりで子どもの世話に明け暮れることの精神的な危険を語った。母親がわが子を手にかけてしまう悲しい事件をよく耳にする。世間はそんな母親を鬼のように言う。だが、そんな母親がわが子を愛していなかったわけではないだろう。誰にも助けてもらえず、乳幼児期の育児をひとりで背負わねばならないとはどういうことか、想像できる父親でありたい、と思った。私は、妻の実家のご両親に、生まれる子が保育所に入るまでの間、私自身も含め、ここでお世話になることをお願いし、快く受け容れていただいた。実際には、妻の頑張りで、里帰り期間は大幅に短縮することになるのだが、産前のこの時期に、先行きの安心を得ておくのは、とても大切なことだった。
大丈夫、この俺を父にしてくれる大(おほ)き温(ぬく)とき掌(て)が天(そら)にある

臨月に入った。いつ連絡が入ってもすぐに駆けつけられるよう、お酒は飲まない。庭の梅が咲き始めた。三月が近づく。

◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆
1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。