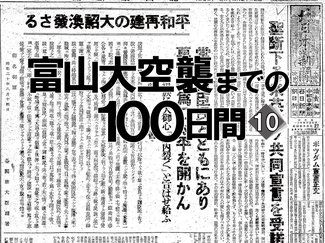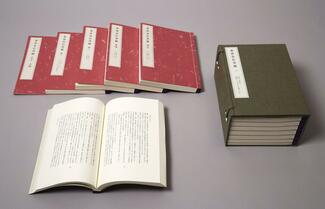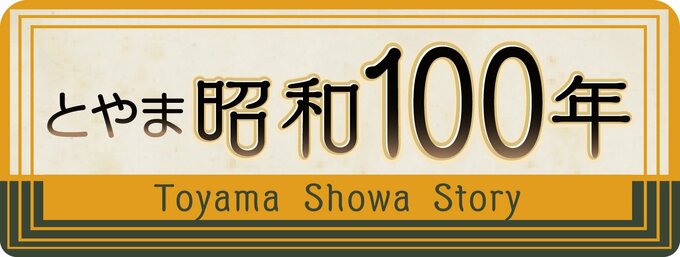「ハンセン病」と聞いて、どんなイメージを抱くだろうか? 現在でも「感染する恐ろしい病気」と誤解している人がいるかもしれない。かつて、国は患者を強制隔離し、全国13カ所の療養所に収容した。その数は約1万2千人とも言われ、富山県出身者もいた。その多くは病気が完治しても古里に戻ることはできなかった。それはなぜか? 激しい偏見と差別のため、帰る場所がなかったのだ。瀬戸内海に強い日差しが照りつける7月中旬、療養所の一つである長島愛生園(岡山県瀬戸内市)の無料見学クルーズに参加し、患者が過ごした環境の一端に触れた。

無らい県運動で強制隔離に拍車
国は1907年、「癩(らい)予防に関する件」という法律を制定し、隔離を開始。1929年には、各都道府県が競ってハンセン病患者を見つけ出し強制的に入所させて一掃する「無らい県運動」が始まった。当然富山県も例外ではなく、積極的に隔離に協力。富山は無らい県を達成した数少ない県でもある。しかし、強制隔離した人数さえ把握していないなど、県の検証は不十分。県内に療養所がなかったことから県民の関心も低い。
とはいえ、県内からはるか遠くの療養所に収容された患者がいたのもれっきとした事実だ。県は2023年まで、県出身者が暮らす全国の療養所訪問を実施し、郷土の名産の寄贈や里帰り事業などで入所者を支援していた。また、かつて大阪市にあった外島保養院には富山県民が数人いたことが記録に残る。
今でも富山から6時間
富山駅から新幹線と在来線を乗り継ぐこと5時間余りで、岡山県備前市のJR赤穂線日生(ひなせ)駅にたどり着いた。さらに長島行きのフェリーに乗り、約1時間の船旅を経てようやく、長島愛生園のある長島に到着した。この長島には、もう一つの療養所「邑久光明園」がある。前出の外島保養院が1934年の室戸台風で、施設が壊滅した後、富山の患者を含めた入所者が移された場所であり、富山と長島の縁は深い。
現代でさえ富山から約6時間も要するのに、当時はどれだけの移動時間だったかは想像もつかない。古里からはるか遠く離れた島に、一人隔離された患者の気持ちはどんなものだったのかは、想像を絶するところだ。
社会と隔絶、そして人権侵害へ
患者はまず、医療関係者とは別の「収容桟橋」にたどり着く。