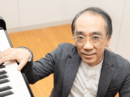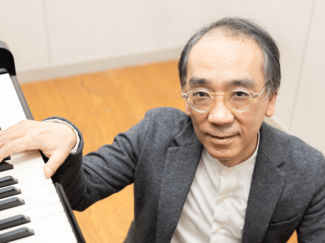——今回の公演で共演する若い音楽家たちは強い決意でこの道に進んだようですが、新垣さんの場合は?
育ったのは普通の家でしたよ。母親が保育士の資格を取る勉強をしていて、そのためにはピアノを弾けないといけなかった。彼女の練習に一緒にくっついていったんです。ピアノはそこからですね。父も演奏会に連れていってくれました。

印象的なのはハンガリー出身のラーンキというピアニストのコンサートです。あの時、雷に打たれたように夢中で聴き入った経験が大きいですね。
やはり葛藤もありましたよ。そのラーンキや、あるいは今活躍している反田恭平さんのような世界的ピアニストになりたいと思う一方で、ちょっと無理だなと気付いていました。生まれ持った何かがあるわけでもないし、練習を積み重ねる根気もない。
でも、ドビュッシーのレコードをかけたら、世の中にこんな美しいものが存在するのかという興奮は止められないんですよ。これはどうやってできているんだろう。自分でも作れるのだろうか。そこから作曲に関心が向かいました。

——その純粋な創作への関心がやがて大きな騒動に結び付いていくなんて誰も想像できません。
私の立場で「ゴースト」を依頼した人を肯定することはできませんが、彼は音楽に強い興味があり、クラシック音楽への憧れがあった。そこは分かるんですよ。私も同じですし……。私は作曲家ですから、誰かのリクエストを受けて曲を作ることは活動の中心。彼のリクエストに応えることには意味があると思っていた。あまりそういうことも言ってはいけないのですが、どうすればよかったのかと、いつも考えています。
——創作者として彼の求めるスタイルで作曲することに葛藤はありましたか。
彼に頼まれて作った曲も自分のスタイルですよ。それに、誰かの要請や世界観に応じて曲を作ることは作曲家ならよくあります。最先端の現代音楽を作っている人が、合唱コンクールの課題曲を作るなんてことは当たり前ですし。映画音楽もそうですね。

——ゴーストライターの騒動があったからこそ、新垣さんという音楽家が世に送り出された。これは運命だったのでは。