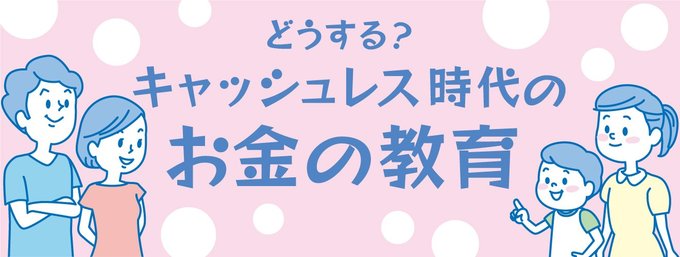前回は、成年年齢が18歳に引き下げられることによる暮らしの変化をお伝えしました。今回は、「自立した消費者」の育成を目指し、小中学校でどのような教育が行われているのかを、県東部教育事務所で社会科を担当する島瀨武夫指導主事、家庭科を担当する吉田みづき指導主事に聞きました。
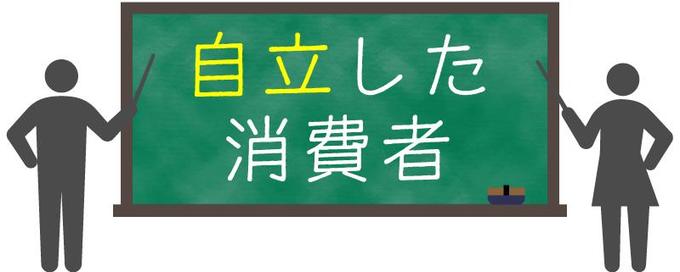
小学校は20年度、中学校は21年度から
消費者教育が拡充
小学校では2020年度、中学校では21年度から、新たな学習指導要領が全面実施となり、それぞれ消費者教育が拡充されました。小学校では社会科と家庭科、中学校では社会科の公民的分野と家庭科で消費者教育について学びます。
社会科について、島瀨指導主事は「消費者と販売者の両方の視点から、環境への配慮などを含め社会全体のこととして学びます」と話します。
「家庭科では、自立した消費者となるために学びます」と吉田指導主事。中学校で学ぶ内容には、新学習指導要領から「金銭管理」と「消費者被害」が加わり、「クレジットカードの普及など、現金を直接目にしないキャッシュレス化が進んでいることや、消費者被害の低年齢化が背景にあります」と説明します。
ここからは教科別に、いつ何を学ぶかを具体的に解説します。
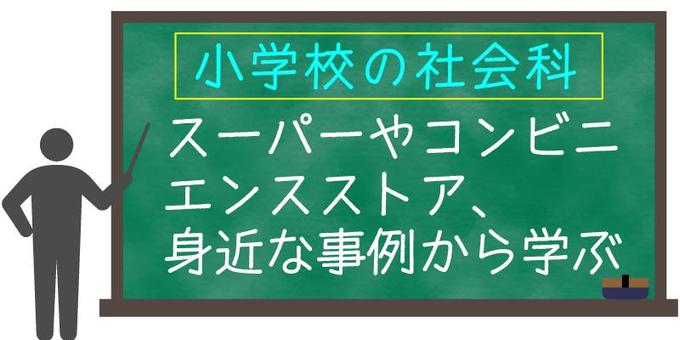
■社会科(小学3年)
▽学習時間 15、16時間ほど
▽テーマ 地域に見られる生産や販売の仕事
▽学ぶ内容(東京書籍「新しい社会3」より)
地域のスーパーに見学に行き、商品の産地を調べたり、店員や来店客にもインタビューしたりする活動を通して、販売の仕事を知る。店のリサイクル活動なども学ぶ。
■社会科(小学5年)
▽学習時間 2、3時間ほど
▽テーマ 我が国の情報と産業との関わり
▽学ぶ内容(東京書籍「新しい社会5」より)
情報を得る手段や、さまざまな産業でどのように情報が活用されているかを理解する。情報通信技術によって、コンビニエンスストアが他の産業とつながり、さまざまなサービスを提供していることを知る。
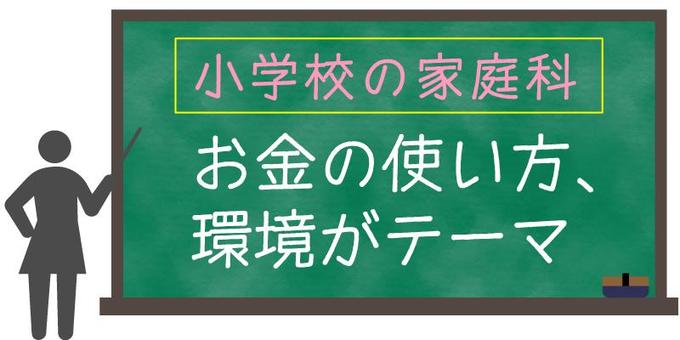
■家庭科(小学5・6年)
▽学習時間 2学年合わせて5、6時間ほど
▽テーマ 物や金銭の使い方と買物、環境に配慮した生活
▽学ぶ内容(東京書籍「新しい家庭5・6」より)
物を選んで管理し、大切に使うという消費者の役割について考える。目的に合った物の選び方、買い方、売買契約についても学ぶ。品質や環境に関連するマークも学習する。
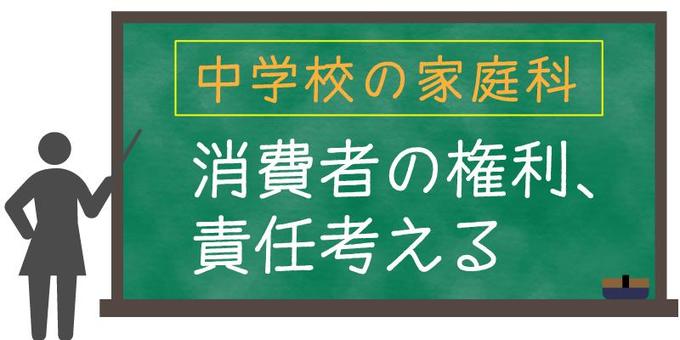
■家庭科(中学1~3年)
▽学習時間 3年間で10~15時間ほど
▽テーマ 金銭の管理と購入、消費者の権利と責任、消費生活・環境についての課題と実践
▽学ぶ内容(東京書籍「新しい技術・家庭 家庭分野」より)
売買契約や購入・支払い方法について理解し、計画的なお金の管理の必要性を知る。消費者トラブルや、消費者の権利と責任について学び、「持続可能な社会」を考える。
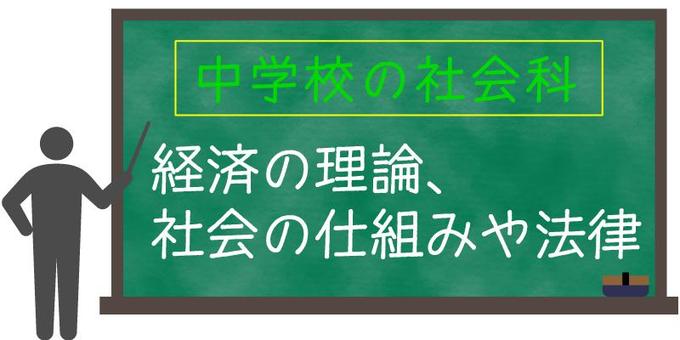
■社会科公民的分野(中学3年)
▽学習時間 25~30時間ほど
▽テーマ 私たちと経済(市場の働きと経済、国民の生活と政府の役割)
▽学ぶ内容(帝国書院「社会科 中学生の公民」より)
市場経済や金融の仕組み、家計の収入と支出、消費者被害について学習する。経済活動のデジタル化についても学ぶ。財政の分野では、歳出や歳入、社会資本、社会保障などに理解を深める。
キーワードは「持続可能」
未来の社会を見据える力つける
どの教科も、キーワードは「持続可能」です。「持続可能」という言葉は、国連が掲げる「SDGs(持続可能な開発目標)」でも、よく知られています。学びを通して、持続可能な社会を目指し何ができるのか、考え判断する力を育てることを目指しています。
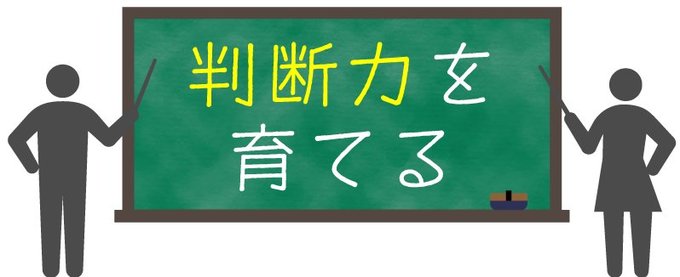
島瀨指導主事、吉田指導主事は「学校での学びを家庭で実践することで、子どもに考える機会を与え、判断力を育てることができます。子どもたちが学校で何を学んでいるかを知り、家庭でもぜひ取り組んでみてください」と呼び掛けます。

次回は、学校での学習を生かした家庭での実践方法を紹介します。