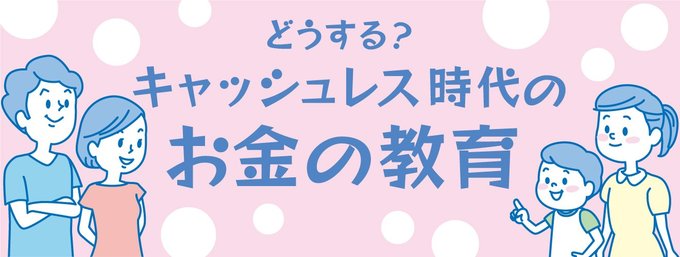きっかけは・・・
コノコト編集長Mが、小学生の娘とスーパーに行った時のこと。会計で娘が私のスマホをレジに差し出す様子を見て、ふと不安がよぎりました。

あらためて振り返ると、お小遣いもまだ渡しておらず、子どもだけで買い物に行ったり、おつかいに行かせたりすることもほとんどありません。
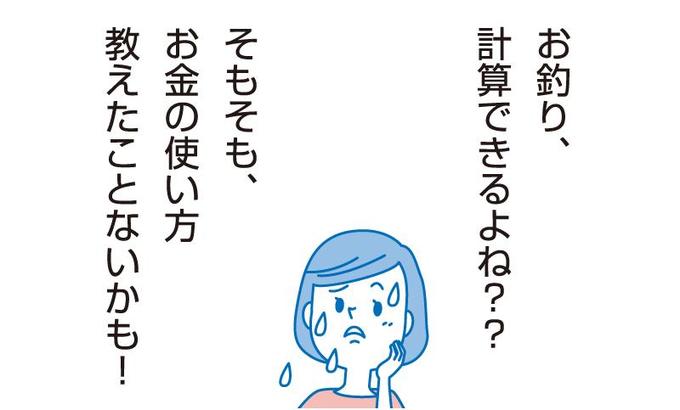
ということで5月下旬、コノコト会員のみなさまに緊急アンケートを実施し、約50人から回答をいただきました。
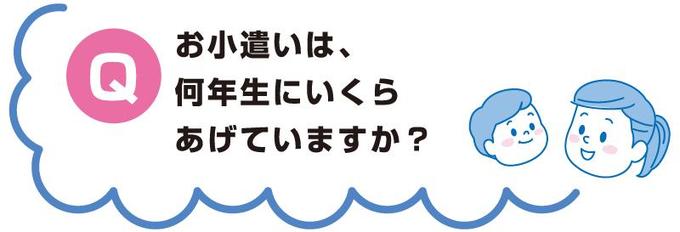
- 小学6年の娘に、5米ドルを換金してお小遣いとして渡している。子どもには、為替レートを見て換金する日を指定させています。
- お金は降ってくるように与えられるものではないという観点から、お小遣いは家事に対する報酬、労働対価として与えている。
そのほか「小学1~6年生は月500円」「小学3年で月300円渡し始め、学年が上がることに100円アップ」「中学1年で3000円」など、渡し始めの年齢や額についてはさまざまでした。
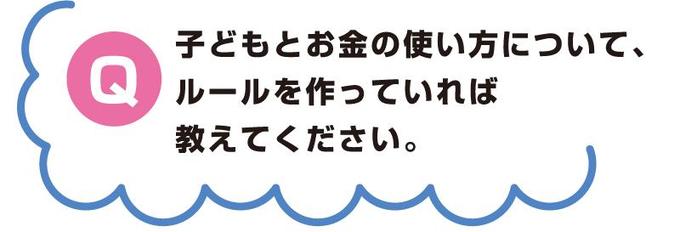
- 友達とお金の貸し借りをしない。
- 友達と買い物に行く時は、事前にいくら持って行くか報告する。
- 学校で使う文房具や衣服は親が支払い、その他(娯楽)はお小遣いの中からやりくりする。
- 無駄遣いしないように、お金の出し入れをお小遣い帳に付ける。
- 何にいくら使うか、ほしい理由を親に説明する。プレゼン次第では使えないこともある。

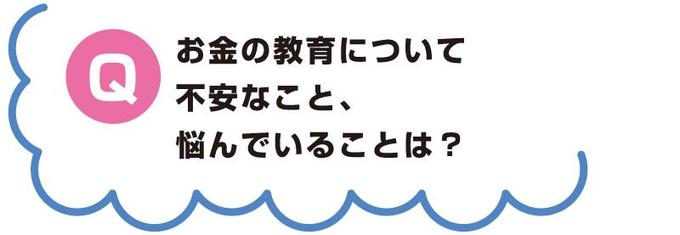
お金が勝手に出てくる? うちの子大丈夫・・・

- 子どもが、お金はATMから勝手に出てくるものだと思っていた。ペイペイやキャッシュカードも、そんな感覚で勝手に出てくるものだと思っている。
- お小遣い帳を書いてもらいたいが、続かない。
- 子どもは、持たせたお金は全て使っていいと思っている。
- 親に買ってもらえないものは、安易に自分で買おうとする。
- 父親が甘く、すぐに欲しいものを買い与えてしまう。
どうやって教えれば?

- 何歳から、いくらお小遣いをあげればいいのか分からない。
- 子どもが必要なものは親が買うので、お小遣いは全く手をつけていないため、お小遣いを渡す意味がないように感じる。渡す金額を増やして、子どもにかかる支出は、全部子どもに任せたほうが、ためになるのかなとも思ったり。悩ましい。
- 自分自身が、現金しか使わないため、それ以外の説明がうまくできない。
自分の時とは環境が違うので・・・
- 一緒にいる時は、なるべく子どもに払わせたいと思っているが、最近のスーパーのレジは早く払わなければいけない雰囲気があり、つい手助けしてしまうため、子どもが自分で考えて払える事がなかなかできない。
- 自分が小さいころは、近所に駄菓子屋と小さなスーパーがあり、自分のお小遣いでやりくりしていた。子どもにもそうさせたいが、生活環境や使う金額の単位が自分の時よりも大きいので悩んでいる。
- おつりの計算や手元にあるお金で欲しいものが全部買えるかなど、お金で買い物できる力は持っていてほしい。その上で、便利なキャッシュレスを使いこなせるようになれば。
教育方針がほしい!
- 家庭で、どこまでお金の教育をするか難しい。親が話したいと思っていても、子どもたちに興味がなかったり、理解ができるかなと思うこともある。この年齢までにこんなことを教えたらいいというような、教育方針があればいい。
- 日本は「お金の話=悪いこと」のようなイメージがある気がする。もっと『お金に働いてもらう事』を身近に感じられるような社会になればいい。
- 単なる貯蓄でなく、為替や運用についても学ばせたい。これから必要なことなので、学校教育にも取り入れてほしい。