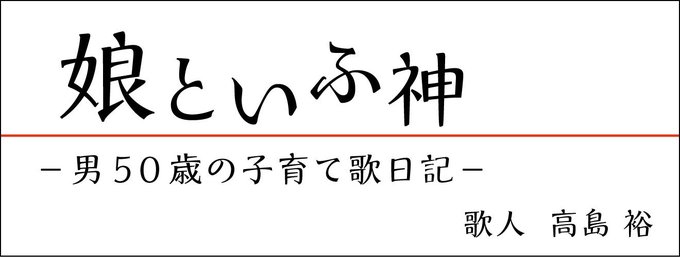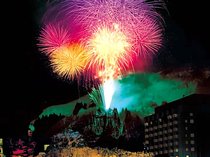娘の保育所生活がスタートし、妻は将来を見据えて、仕事を増やそうと動き始めた。
そんな頃、北日本新聞社の田尻さんから、ウェブサイトでの、この連載のお話をいただいた。五十才近くなって初めて父親になった私の日々の思いを、短歌とともに綴ってゆくという企画である。高齢の父親の目線から子育てにアプローチし、それを短歌と絡めてゆくというのは、今日とても意味深く、やりがいのある仕事だ。一方で、短歌愛好者に限らない広い読者に向けてまとまった文章を書くのは初めてで、緊張して連載開始に臨んだ。
娘は、時に風邪をひいて熱を出したりしながら、順調に成長してゆく。名前を呼ばれて手を挙げるようになる。ハイハイが上手になる。「ワンワン」「ブーブー」などなど、言える言葉も増えてゆく。何かあったら遠方から駆けつけてくれる妻の実家の方々に助けてもらいながら、すくすくと育ってゆく。
そんな日々の中、グループホームの母は、身体能力の衰えから、老健施設へ移転した。頸部にはガンが見つかっていたが、九十歳近い老齢で認知症でもあり、手術の難しい部位でもあるので、治療を断念し、残りの時間を穏やかに過ごしてもらうことを選んだ。
その母が、老健移転後まもなく、腸閉塞を起こして系列の病院に入院した。昔から、胃腸の具合が悪くなって何も食べられなくなることがよくあったので、今回もそれだろうと軽く考えていたが、医師は思いのほかシビアな見方をしていて、ガンの転移による機能不全の可能性が高いとのことだった。覚悟していることとはいえ、母の死が現実として目の前に迫ってくると、胸に鉛を抱いたように、暗く悲しい気持ちに囚われてしまう。
妻は子育てに忙しい中、姉と一緒に医師の話を聞き、母の身の回りを整えてくれた。マッサージの技術を持つ実家のお母さんに来てもらって、母の身体をほぐしてもらったりもした。
幸いにも、今回の腸閉塞はガンとは関係のない一時的なもので、やがて母は回復してゆき、食べられるようになった。私たちはある夕方、娘を連れて母を見舞った。母は大変喜んで、ただ一人の孫に笑顔を見せた。娘は、病室のベッドに横たわる祖母の姿を見て最初は泣いたが、やがて笑い顔を向けてくれた。私が娘を抱っこして母に向き合わせている間、妻は、伸びてきた母の爪を切った。家族四人が集ったこの夕方のひとときを、私は忘れないだろう。
記憶には残らぬだらう、さればこそ何度でも笑へおまへの祖母に
つかまり立ちができるようになっていた娘は、数秒間手を離して立っていられるようになり、ほどなく、二、三歩歩けるようになった。自分自身の意志で、立ち、歩こうと日々挑戦を繰り返す娘と、人生の終わりに向けて少しずつ身体機能を閉ざしてゆく母。切なく、愛おしく、生命の繰り返しを思った。

◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。