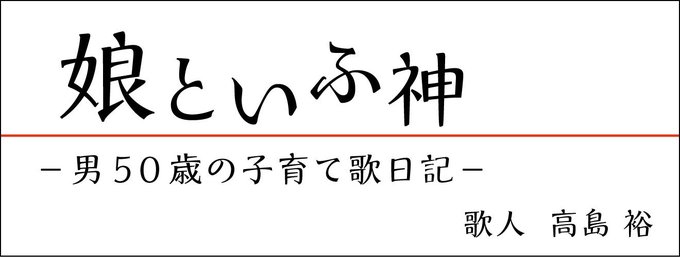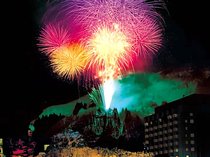娘が生まれた年も、暮れようとしていた。大晦日、私たちは娘を連れて、近くのショッピングモールへ正月の買い物に出かけた。その一画に、ひな人形の特設売場があり、足を止めた。昔のような豪華な七段飾りではなく、男雛女雛一対だけの親王飾りのものばかりだったが、それでも、何事につけ効率が優先される時代の中で、手作りの優しさ、細やかさが静かに発光しているようで、見飽きなかった。ひな人形には厄払いの意味があり、親や姉のお下がりで全部済ませるべきではないという話を聞き、娘のためのひな人形を買ってやりたいと思っていたところだったので、その場で選んで購入した。背景の衝立が木でできた、落ち着いた雰囲気のものを選んだ。表情の優しさもポイントだったが、売場の人の話では、手作りなので、展示品と実際に送られてくるひな人形とは、表情は微妙に違うかも知れない、とのことだった。
さて、私たちには、結婚前から二人で飼っている猫がいた。「饕餮(とうてつ)」と名付けて、私の歌集のタイトルにもした。結婚して夫婦となり、いろんな問題に向き合いながら二人の暮らしを作ってゆく日々を、いつもそばにいて癒し、励ましてくれた大切な存在だった。子猫の時にさ迷っていたのに妻が出会って飼い始めてから七年になる。やんちゃなオスだったが、その饕餮が腎臓を病んでいるとわかったのが一年前。それでもしばらくは元気で、生まれてきた娘のそばで寝たりもしていた。娘が生後七日を迎えた日、私たちはおそるおそる娘と饕餮とを引き合わせたが、その時娘が目をまん丸にしてびっくりしたような表情をしていたのと、饕餮がこの生き物は何だろうとしきりに鼻を近づけてクンクンしていたのをはっきり覚えている。
その饕餮に、終わりの時が近づいていた。私たちは、毎晩娘が寝ついた後、嫌がる饕餮の背に針を刺し、点滴した。そうしないと体に毒が回って死期を早めてしまうからだ。私たちは、饕餮にとってどうするのが一番幸せなのかを考え、迷った。一切の治療をやめてしまうという選択もあったが、まだ点滴に耐える力が残っているうちは、共に過ごす時間を少しでも伸ばしたいと思った。

二月。饕餮はいよいよ何も食べなくなった。背骨が見えるまでやせ衰え、トイレに行っても外にこぼしてしまう。それでも何とか舌で毛づくろいをしているのがいとおしい。もう点滴も、薬を飲ませるのもやめることにした。
一方娘の方は、すくすくと成長していた。這って移動するのが上手になり、私たちの口真似をして「ア、イ、ウ…」などと発声するようになった。私たちには、無垢な二つの生命が、しばしば重なって見えた。
座敷に飾った娘のお雛様。表情は期待通りの優しさだった。饕餮の命あるうちにと、私が娘を、妻が饕餮を抱いて、雛飾りの前で一緒に写真を撮った。ちょうど来られていた妻のお母さんに、スマホのシャッターを押してもらった。饕餮は、瀕死状態とは思えぬほどに、くりくりとした目で、可愛く写っていた。
それから十日足らず後、饕餮は息を引き取った。私たちに娘が生まれ、順調に成長してゆくのを見届けての、お別れだった。
ありがたう、ありがたう、われら人語もて
送るほかなし、無垢のいのちを
◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆

1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。