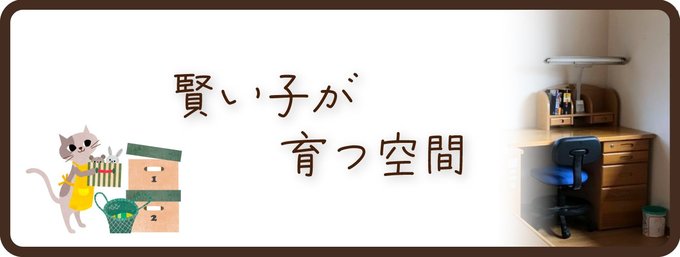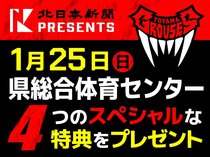この記事が皆様に読まれている頃。我が家の一人息子は、大学生として、一人東京で、不安と期待の毎日を送っているものと思います。共働き3人家族の18年間は、本当にあっという間でした。ここでは、そのかけがえのない母としての経験と、住宅業界での家づくり、または整理収納アドバイザーとしての経験と知識を、現在子育て真っ最中のご両親に向けて、参考になればと書かせていただきます。
賢い子ってどんな子?
今後、大学受験が大きく変わるように、知識が豊富な子が賢い子という時代ではなくなりましたね。
私が考える現代の賢い子の定義は、
- 「かんがえる力がある子」
- 「しゅうちゅうりょくがある子」
- 「コミュニケーション力がある子」
- 「いきる力のある子」
この4つではないかと感じています。
そして、そんな賢い子が育つ舞台は、学校ではなく、家という住空間であり、そこに住む家族という社会の中で育まれていきます。
考えることができる子の住空間とは
ズバリ、好奇心を刺激する空間だと思います。
先日、ある住宅会社様で収納セミナーをさせていだだいたとき「浮田さんがいう収納にすると、大人が求めるデザイン性や雰囲気を壊してしまうことになるのですが・・・そうしたくない場合、どうしたらよいですか」と、若いご夫婦から質問をいただきました。
私の答えはこうです。
「私の経験では、子育てはあっという間です。子育てが終わるまでは、子どもさんを中心に、そのあとでも大人の空間を楽しむ時間は十分にありますよ。」
残念ながら、子どもの考える力を育てる空間と、大人が落ち着く空間は反比例するものだと私は感じています。
リビング空間には、親子共有の本棚を置こう
子どもの好奇心を刺激するには、図鑑・辞書・地図が良いと言われていますね。そんな本を置く場所は、子ども部屋ではなく、リビング。そして、収納のかたちは扉がないオープンタイプの棚をおすすめします。もっと言うと、ひとつの本棚に大人と子どもの本を同居させるのもポイントです。
視界に入ってくる色や文字は、見えているだけで脳を刺激しますから、本がいつも見える状況というのは、くつろぐという大人の目的を邪魔することになります。しかし、子どもの思考力を中心に考えたときは、興味や疑問を持った時、すぐに調べることができる環境が適しています。また、親が楽しそうに本を選んで読んでいる姿を見せるのも効果的ですし、子どもが本に親しみやすくなります。いつか自分もお父さんのような難しい本を読めるようになりたいという憧れから本が好きになることもあるでしょう。

ただ本を置いても考える子にはならない
以前、小学生の男の子2人の子育て中のお宅にお邪魔しました。本を読む子に育てたいという理由で、リビングの一角に本棚を置いてありました。ただ、ほこりがかぶっていて使っているように見えなかったので聞いてみると、読んでいない様子です。私も本を読む子にさせたかったので、気持ちはとてもよく分かるのですが、置いてあるだけでは本を読む子にはなりません。
図鑑なら、まずは親が楽しそうに見る、一緒に調べる、調べたものをリアルに見に行くなどの工夫が必要になり、それは、親の私たちが、時間や気持ちにゆとりを持つことが必要となるようです。もし、そうした眠っている図鑑や辞書があれば、配置の工夫だけでなく、関わり方を少し変えてみるとよいのかもしれません。
環境が人をつくる
うちの息子は、大好きな父親が読んでいる本に興味を持ち育ってくれたので、賢いかどうかは別として、本を読む習慣が身につきました。特に、小説が好きなのですが、将来は、何かしら表現する仕事に就きたいと夢を語ってくれます。住まいに関わる仕事に就いて、いつも感じているのが、「環境が人をつくる」ということ。考える力がある子を育てるには、好奇心を刺激するものを視覚に入れ、それを親も一緒に楽しむことが必要なようです。
【次回】②集中力がアップする空間

◆浮田 美紀子(うきた・みきこ)◆
整理収納アドバイザー、骨格スタイルアドバイザー、家事代行会社経営。
富山市出身。住宅関連企業を経て2012年に整理収納アドバイザーとして活動を開始。県内の主婦グループ「シュフーレ」を立ち上げ、暮らしに関連する講座を担当する。2016年に家事代行や整理収納のほか終活サポート、宅食サービスなどを行う会社を設立。大学生の長男がいる。