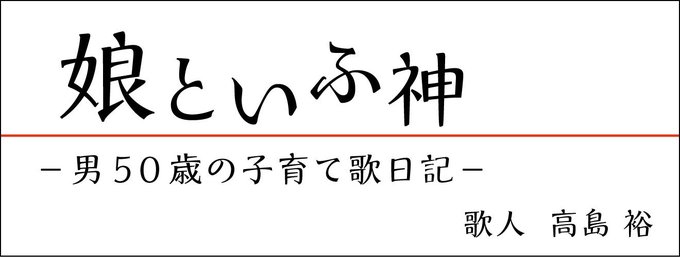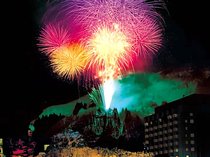えっ?一瞬、夢の中にいるような、ふわっとした感覚に見舞われた。続いて、自分の輪郭があたたかく溶け出すような、不思議な気分になった。身体の芯からやってくる、深い深い喜びの感情だった。
夕方、職場のPHSに入った外線電話で、妻から「妊娠してたよ」という知らせを受けた時の、私の気持ちである。
よかった、よかった、という声が、自然と湧き出してきた。それ以外の言葉は、何も思いつかなかった。今から二年近く前の、梅雨晴れの日だった。

その当時、私は四十八歳。二十代に始めた短歌(よく俳句と間違われるが、五七五のあとに七七が付く方だ)を続けながら、会社員をしている。そして、グラフィックデザイナーである妻は八歳年下、子どもを産むのには、年齢的なリミットに近づいていた。結婚して四年、私たちには子どもがおらず、一度不妊治療(体外受精)も試みたが、妊娠には至らなかった。
俺は自分の子どもが欲しいのか、と何度も自問してみた。車が欲しい、とか、洋服が欲しい、とかいうふうに、明朗に「欲しい!」と即答できるような性質の問いではなかった。逆に、このまま自分の子どもは持たなくていいか、とも自問してみた。そのたびに、「それでいい」とは言わせない何かが、自分の中にあるのを感じた。それが何なのかは自分でもよくわからなかった。
もちろん、子どもが欲しくても授からない人もいるし、子どもを持たないという選択をする人もいる。どの道を辿っても、人生の価値には変わりないだろう。ただ、自分自身が、この世にかけがえない身体を持って生まれ、親や周囲の人たちに育てられて大人になったという事実は、決して否定できない。子育ての苦労がどれほどであっても、子どもを授かるために、できるだけのことはしたい、というのが、偽らざる思いだった。
けれども、実際に身体を痛めるのは妻である。男の側の勝手な思いを押し付けることはできない。私は、妻の気持ちを第一に尊重しようと思った。
最初の不妊治療のとき、医師に、受精した胚の顕微写真を見せてもらった。泡が三つ四つくっついたような画像だったが、懸命に生きようとしているのだと思うと、愛おしく感じられた。それが妊娠に至らなかったことが傷ましくて、妻はひどく嘆いた。自分でお腹に注射し、身体の変調にも耐えながらの苦しい治療の果ての、この結果だった。
もちろん、体外受精の成功率は低く、それを承知の上で試みたのだったが、妻のこの様子を傍で見ていて、「もう一度」とも「もうやめよう」とも言えなかった。
後悔のないようにしたい、という妻の確かな言葉を聞いて、再度不妊治療を試みることに同意した。これでもし妊娠しなかったら、二人で生きてゆけばよい、と話し合った。妻は、前回ほどには苦しそうな顔を見せず、事は進んだ。そして、あの知らせが届いた。
外線の声はかすかに湿りつつひとつ生命(いのち)の灯れるを言ふ
予定日は翌年三月。私は四十九歳で父親になるのだ。

◆高島 裕(たかしま・ゆたか)◆
1967 年富山県生まれ。
立命館大学文学部哲学科卒業。
1996年「未来」入会。岡井隆氏に師事。
2004 年より8年間、季刊個人誌「文机」を発行。
第1歌集『旧制度』(第8回ながらみ書房出版賞受賞)、『薄明薄暮集』(ながらみ書房)などの著書がある。
第5歌集『饕餮の家』(TOY) で第18 回寺山修司短歌賞受賞 。
短歌雑誌『黒日傘』編集人。[sai]同人。
現代歌人協会会員。