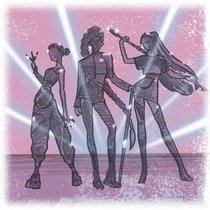金沢市は日本で生み出される金箔の100%を生産しています。とはいえ、工房は片手で数えられるほどしかありません。なかでも「箔座」は、中尊寺金色堂や西本願寺をはじめとする国宝や重要文化財の修復に使われる「縁付金箔」を供給している数少ない工房のひとつです。縁付製法は、2020年末にユネスコ無形文化遺産にも登録された、400年の歴史をもつ日本固有の伝統技術です。

金沢が金箔の里として栄えた背景には何があるでしょうか。まずは、加賀藩前田家による文化振興策があります。1593年に前田利家が金銀箔類の製造を命じたことから金箔の製造が始まりました。次に、高質な水・高い湿度という風土。金箔製造にとって静電気は大敵なので、雨の多い北陸の気候は理にかなっていました。さらに、地道な作業を粘り強く続ける地域の気質とも相性が良かったのです。おまけに地名に「金」があります。
高質な水がなぜ重要になるかといえば、金箔を挟む打ち紙づくりに必須だからです。藁の灰汁や卵などを仕込み半年以上かけて作られる特別な紙は、金以上に大切とされ、「まま紙」とも呼ばれています。「これさえあれば、おまんまが食べられる」という意味です。独特の風合いをもつこの打ち紙こそが、金箔の繊細な光沢と質の良さを生む要となります。数回使用した打ち紙は、なんと化粧用のあぶらとり紙として再利用されます。あぶらとり紙の起源が金箔の打ち紙だったとは。

実際に「箔座」の工房を訪れました。量産向けの現代的製法、「断切」で金箔を打つ職人、箔でアクセサリーをつくる職人、箔にアート加工を施す職人など、多彩な専門技術をもつ人々が集まっています。工房には「金箔専用」と書かれた掃除機があります。一片たりともムダにせず、再利用するのです。打ち紙も金もサステナブル。
さらに奥へと進み、「縁付金箔」を打つ職人の仕事場に入りました。長年、縁付金箔をつくり続ける職人たちが作業をしています。「やってみるか?」と言われ、挑戦してみました。竹で作られた自家製の道具で、1万分の1ミリという薄さの箔を正方形に裁断していくのです。一見、単純に見えますが、力加減が極めて難しい。力を込めすぎれば箔は割れ、弱ければ切れません。職人の太田武敏さん曰く「きれいに切れるときは、箔の音が聞こえる」。素人にはまったく聞こえない「金箔の声」を聞き分けるその耳は、何十年も箔と向き合って育てられたもの。縁付製法に携わるこうした熟練職人は、金沢全体でも、今や高齢になった数人しかいません。
金箔は寺社建築だけでなく、ホテルの内装から食器、アート、コスメに至るまで用途を広げ、時代に合った新たな輝きを放っています。薄く儚げでありながら、人の手が加わることから生まれるあたたかみのある光が周囲を照らし、心を満たします。
職人の耳に届く金箔の声を後世に伝え、さらなる創造へとつなげていくことこそ、未来の日本のラグジュアリーの礎となります。工房の扉は開かれており、次世代を待っています。