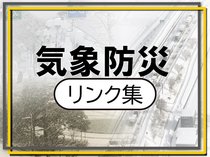とろ~りとした黒糖のたれがたっぷり絡んだ「あやめ団子」。実は、富山市独特の味覚だとご存じだろうか。昔は、名前の通りアヤメの咲く頃に売り出す季節限定商品だった。昭和30~40年代ごろから作っており、あやめ団子が看板商品となっている「石谷もちや」を訪ねた。
石谷もちやの中央通り店では、注文を受けてから黒糖のたれを絡める。団子は香ばしくて温かく、口の中でとろけるようにやわらか。素朴な甘さと、この食感が癖になる。
水分たっぷり 夏の団子
「アヤメの花が咲くのは5月頃。あやめ団子は5月から夏にかけての季節商品だったんです」。そう教えてくれたのは、石谷もちやを経営する石谷餅店の社長、石谷悦男さん(50)だ。

石谷さんによると、団子は寒い季節の方が売れ、暑いと売れにくい。「でも、あやめ団子なら水分が多くて夏でも食べやすい。夏の団子だったんです」
季節商品だったあやめ団子の味が評判を呼び、来店客の要望に応えて通年で作るようになった。いつしか、石谷もちやを代表する味になった。石谷さんは「少なくとも30年くらい前には既に看板商品だった」と振り返る。
シンプルだからこそ 素材・製法にこだわり
あやめ団子の正確な由来は分からないが、6月の日枝神社の「山王まつり」で売られ、富山市民に親しまれてきた。製法自体は、団子に黒糖を煮詰めたたれを絡めるというシンプルなものだ。

石谷餅店であやめ団子を作り始めたのは石谷さんの祖父、故豊次郎さんだった。実は石谷家は明治時代、餅ではなくせんべいを作っていた。豊次郎さんは婿養子で、東京の和菓子店で修業していた経験を生かし、餅店に転換した。
豊次郎さんはシンプルな団子だからこそ、素材と製法にこだわった。団子は上新粉を使うが、もち米も少し混ぜて粘りと甘みを出す。黒糖は沖縄の波照間島から取り寄せた。黒糖を水に溶かして弱火で煮込み、片栗粉でとろみを付ければ、たれの完成だ。微妙な火加減、煮詰め具合が味を決める。
当初は、紙のように薄くスライスした木で団子を包み、新聞紙でくるんで提供していた。

繊細な風味が味の決め手
豊次郎さんが考えた製法は今もほとんど変わらず、受け継がれている。
石谷さんには、祖父のこだわりの大切さを痛感した出来事がある。10数年前、黒糖の仕入れが難しくなり、急きょ別の産地の黒糖を使ったところ、「風味が全然違った」。団子にもち米を混ぜる製法も「米のうまみが加わり、もちもちとした独自の食感につながっている」。
もち米を混ぜると、団子はまとまりにくくなる。機械で対応できない部分も出てくる。石谷さんは時には「おじいちゃん、なんでこんな大変な方法にしたの」と思うこともあるそう。でも、「お客さんは分かっていらっしゃる。おいしいから愛し続けてくれる」。

「飲み物みたい」!?
ところが、あやめ団子を作る店は年々減っている。1995年の北日本新聞には