砺波市では市内の小中学校すべてに同じ管理システムを導入しています。出町中学校(生徒数645人)では2012年度に導入し、2014年5月から本格稼働させました。生徒玄関から入って目の前に位置する図書室の蔵書数は15,376冊(2022年10月12日現在)。すべての本にバーコードのラベルシールが貼り付けられていました。

簡単になった貸出手続き
2021年度の生徒1人当たりの平均貸出冊数は20.5冊で、システム導入前の2011年度の7.2冊から3倍近くに増加しました。徐々に冊数が増え、近年は20冊程度で推移しています。松本美紀学校司書は「手軽に借りられるようになったことが大きい」と理由を説明します。出町中もシステム導入以前はカードに本のタイトルや日付を記入する手続きが必要でした。今はピッとバーコードを読み取ってもらっておしまいです。
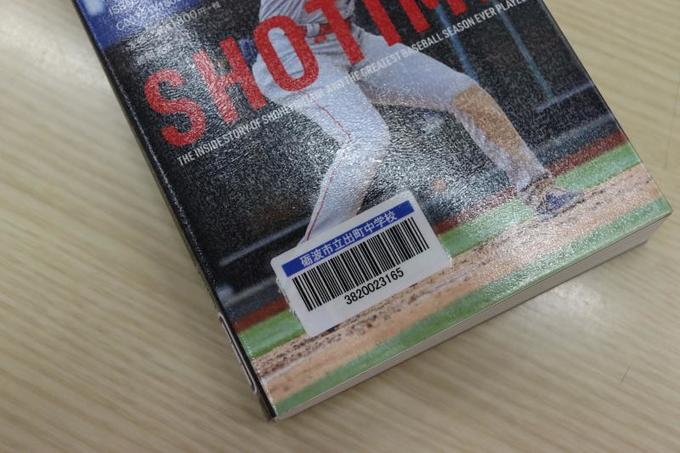
手書きの貸出カードは面倒なうえ、小学校1、2年生の児童にはやや高度な要求です。また誰がどんな本を読んだかという記録が残る方式ではプライバシーを侵害する恐れもあります。自分がどんな本を読んだかを他人に知られたくないと感じる人は大勢います。
システムを導入したことで、貸出データ、延滞データなどが瞬時に得られ、学校司書が図書室運営の充実に生かすこともできます。新しく購入した本の登録も、あらかじめ付与されているISBNコード(国際標準図書番号)を読み取れば完了します。学校図書室共通の悩みである紛失本についても出町中では4~5年前から極端に減り、ほぼないといってもよい年もあるそうです。

自治体によってばらつき
良いことづくめの蔵書管理システムですが、課題は費用です。商品によってコストはさまざまですが、導入費用のほか、年間コストがかかるケースもあります。砺波市が導入しているシステムは年間コストとしてライセンス料約1万円のほか、ラベルシールなどの費用がかかります。富山県図書館を考える会(江藤裕子代表)の調査によると、砺波市のほか、富山市、射水市、小矢部市、立山町で全小中学校にシステムが配備されている一方、まだ、司書が手作業で管理している自治体の学校もあるといいます。
文部科学省が進めるGIGAスクール構想で、「以前は図書室に来て取り組んでいた調べ学習もタブレット端末で完結することが多い」と残念そうに話す司書さんもいます。江藤代表は「子どもの読書離れが言われる中、学校の中にある図書室は誰でも自由に通える大事な存在。一層充実させる必要がある」と指摘しています。






