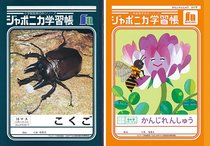県内の公立小中学校の給食1食あたりの単価は265~305円(小学校)、300~370円(中学校)です。

富山市は4月から1食あたりの単価を小学校で274円から298円に、中学校で323円から350円にアップ。保護者負担は月額で500円アップし、小学校5800円、中学校6800円になりました。
同様に上市町は単価を小学校で265円から290円へ、中学校で300円から330円に上げました。町が一部補助し、保護者負担は月額で小学校が400円アップの4000円、中学校が600円アップの4800円になりました。
原料や輸送費の高騰を受け、食材が値上がりしているのが理由です。揚げ物用油を筆頭に野菜や肉など軒並み価格が上がっているといいます。
炊き込みご飯の回数減らす
学校給食は、おなかが満たされればそれで良し、というわけにはいきません。
国が子どもの成長に必要な栄養素、塩分量、エネルギーなど細かな基準を示しています。現場では栄養教諭や管理栄養士が、限られた予算の中でこの基準に沿う献立を実現しようと努めています。低価格のみを追求するわけにもいきません。
現場の声を聞くと…
「質を落とさないよう、できるだけ安い食材を探します」(砺波市)
「肉の部位を変更するなど低価格の食材選びを心掛け、おいしさや栄養価、量が確保できるような献立作りと調理を行っています」(黒部市)
「これまで上乗せしていた分の量を少し減らしています」(県東部の給食センター)
「デザートなど〝お楽しみ〟の回数を調整しています」(高岡市)
高岡市教育委員会によると、高岡市ではおよそ1年前に献立を決めます。予算内に収まるよう計算しますが、実際に購入する際の価格が見通しをさらに上回ることがあると言います。
値上げに踏み切る
毎日、約33000食を提供する富山市。前回、価格を改定したのは2016年度でした。
富山市教育委員会もこれまで
▽主菜のサイズを調整
▽炊き込みご飯の回数を減らす
▽果物のサイズを小さく
▽牛乳の代わりに小さなジュースを付ける
▽安い野菜を使う
といった対策で乗り切ってきましたが「このままでは栄養バランスが取れ、かつ、楽しみのある給食の実現が困難」として、値上げに踏み切りました。
現在は、果物のサイズや炊き込みご飯の回数は従来の水準に戻り、時には子どもたちが大好きなジャムも付けられるようになりました。
また、食物アレルギーのある子が、みんなと同じ献立を食べられるよう配慮することも可能になったそうです。
例えば、カレーに混ぜ込んでいたチーズを個包装のチーズに変更すれば、乳のアレルギーがある子もカレーはみんなと同じものが食べられます。
市教委学校保健課の宮前仁課長は「いっそう充実した給食を提供したい」と話しています。
値上げは保護者の負担増になりますが、現時点で富山市や上市町の教育委員会に保護者からの苦情はないそうです。

この事態を受け、国は4月、新型コロナの臨時交付金を「給食に活用することが可能」と示しました。ただ、現在の国際情勢を考えると、2学期以降の食材価格の推移は不透明な状況です。「業者から今後の見通しが立たないと言われている」(県東部のセンター)、「いつまでこの状況が続くか分からない」(県東部の市教委)と途方に暮れる担当者もいました。
黙食でも楽しい時間に
文部科学省は、給食に「学習教材」の役割を持たせています。肥満や朝食抜きといった食生活を改善するために、給食を通して子どもたちに正しい知識を身につけてもらうのが狙いです。
給食は限られた予算の中で、「栄養」「お楽しみ」「食育」の役割を果たさなければならず、現場は難しいかじ取りを迫られています。高岡市教委学校教育課保健給食係の堀内麻由係長は「安全安心な給食を届けることが一番ですが、コロナ下の黙食の中でも、給食が楽しい時間であるように工夫したい」としています。