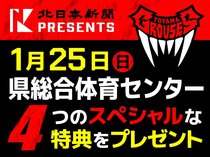雪国・富山では、真夏でも雪合戦が楽しめる? そんな話を聞きつけました。その正体は、富山発祥のニュースポーツ「Cling(クリング)」です。体験会を訪れると、雪こそありませんが、逃げ隠れしながら白い球を投げ合う様子はまさに雪合戦。この日は、小学生から社会人まで、プロハンドボール選手も参加し、年齢も体力差も関係なしの真剣勝負を繰り広げました。子どもも大人も、プロスポーツ選手もはまる、その仕掛けとは?

大人が大苦戦
すばしっこく走る子ども有利
8月上旬、射水市のビルト・プレイズ歌の森体育館で体験会が開かれ、小学3年から6年の児童と、同市を拠点とするハンドボール日本リーグ女子「アランマーレ」の選手らが参加しました。
子どもと大人が混じった4人組4チームに分かれ、それぞれ赤、オレンジ、黄、緑のベストを身に着けました。ベストは、面ファスナーの柔らかいほうの生地で作られており、雪玉代わりのボールがくっつく仕掛けになっています。ちなみにボールは、綿に面ファスナーの硬いほうの生地を巻き付けてあり、こちらも軽くてふわふわです。

チーム対抗で1分間、球を投げ合い、ベストにくっついた数が少ないほうが勝ち。同時に持てるボールの数は、片手に1個ずつです。今回はコート内に約50個をばらまきました。
参加者は、ボールが当たらないよう体をのけぞらせたり、障害物となるテントに隠れたりしながら、攻撃のタイミングを狙います。

すばしっこく走り回る子どもが、大人を挟み撃ちすることも。雪合戦と鬼ごっこを合わせたようなゲームです。アランマーレの横嶋遥選手は「本気を出しましたが、たくさんのボールをつけられてしまいました。子どもはベストが小さいので『的』も狭いですから」と息を切らして話します。


子どもたちは、充実した笑顔を見せます。小学5年の女児(富山市)は「テントに隠れていたら攻められたので、自分からボールをくっつけようとよく走った」と振り返ります。
子どもも、大人も、障害の有無も関係なく
考案したのは、高岡市でデザイン会社を営む木村嘉宏さん(33)。デスク作業が中心で運動不足に悩んでいたことから、道具や費用が少なく、専門的な技術も不要で、気軽に始められるスポーツを…と探すうち、自分で作ろうと考えるようになりました。さらに3人の娘を育てる立場から、子どもの体力作りにもつなげたいと、ルールや道具を試行錯誤し、2018年に誕生したのがクリングです。

「Cling」は「くっつく」を意味する英語です。スポーツが苦手な人にも親しみを感じてもらえるよう、木村さんはプレー中も「ボールを当てる」ではなく、「くっつける」という言い方をしています。さらに「運動能力や障害の有無に関係なく楽しんでほしいので、参加する人数や勝敗の決め方は、自由に設定してほしい」と呼び掛けます。
ボールは5、6グラム
あえて真っすぐ飛ばせない
ボールにも、運動量、安全性を向上させるため、さまざまな工夫が施されています。直径5~5・5センチで、5、6グラムと軽く、真っすぐに飛びません。「敵と近い距離でないと、狙い通りにボールをくっつけられないようにしました。参加者にたくさん走ってもらうためです」と意図を語ります。形は完全な球体ではなく、少し角張っています。球体だと床で転がり、参加者が誤って踏んでけがをする心配があったためです。

手縫いするのは木村さんの母親で、一つ作るのに20分ほど、強度を保つため野球ボールの縫い方を参考にしました。現在の形になるまで10回ほど試作していますが、より良い形にしようと改善を続けています。
特別支援学校・保育園の活動として採用
教育現場での活用広める
今春、クリング協会を立ち上げました。メンバーは、会長を務める自身を含めて4人。教育・福祉機関や企業、地域を対象とするイベントの主催、道具の販売、レンタルなどを行っています。これまで、富山県内で20回ほどイベントを開いていますが、今後は、全国で展開したいと考えています。
また、木村さんは、特に学校教育での活用に力を注いでおり、これまで特別支援学校や保育園の活動にも取り入れられました。
プレーする人を選ばないクリングは、今後、さらに多くの人に健康と笑顔を届けていきます。