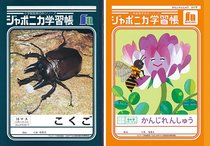「親が共倒れとなった場合の子供の面倒は誰がみるのか」。夫婦で新型コロナウイルスに感染したフリーアナウンサーの赤江珠緒さんが、不安な気持ちを綴った手記(出演するTBSラジオのHPで発表)が関心を集めています。

夫の陽性が判明し、自身と2歳の長女の検査結果を待つ間に書かれたもので、「罹(か)った場合、なるべく体力的にも、精神的にも軽めに治す」という目標のため、いろいろ準備をされたそうです。
①2週間分の隔離生活の用意をスーツケースなどにまとめる。
②家を片付ける。消毒もやりやすく、体調に異変のない家族の運動スペースに。
③玄関前に食品などを届けてくれる場があるか確認。
④外へ出られないので、他のけがや病気のための置き薬の準備。
⑤子どもの面倒を誰がみるのか。これについては解決策が見いだせず、「夫と私の発症のピークがせめてずれる事を願うばかりです」と記しています。
預け先なければ 児相・市町村に相談を
同様のことが富山県内でおきた時、どうしたらよいのでしょうか。県健康課では、お世話が必要な陰性の乳幼児がいる場合「まずは親族や知人に預けることができないか相談してほしい」としています。
しかし感染のリスクから、特に高齢の祖父母に預けることは難しく、頼る人がいないことも考えられます。その際は「児童相談所(児相)や市町村の子育て支援の関係部署に相談してほしい」とのことでした。
不安の声は感染拡大とともに高まり、大阪府は24日、保護者が感染し子どもの養育が難しくなった場合、児相が一時保護し、ホテルなどの宿泊施設で預かる方針を明らかにしています。
子どもが感染 親は陰性
面会は子どもの年齢、親のリスク…ケースバイケースで判断
子どもがコロナに感染し、親が陰性のケースもあります。現在、県内の多くの病院、福祉施設ではコロナへの感染防止から、家族の面会が厳しく禁止されています。子どもが感染した場合の親の面会について、県健康課は「子どもの年齢や症状、親の感染リスクを踏まえ、入院する病院の判断となる」としています。
日本小児科学会が23日発表した「小児の新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制に関する見解~入院や付き添いの考え方も含めて~」では、「小児が入院した場合には、保護者の同室付き添いが考慮される」としています。保護者によるケアは精神的な安定につながり、医療従事者の負担も大きく軽減し、症状の急変の兆候にも早く気付くことができることなどが理由です。ただ保護者も濃厚接触者となり、病室から出られなくなります。
※同学会では、小児、保護者の症状別に、対応についての考え方を示しています。
家族であっても簡単に会えなくなるかも
感染対策 再確認を
子どもがつらいときに、そばにいることができないー。親にはとてもつらいことです。自分たち家族に、このような状況が起こるかもしれないと考えれば、今の自粛生活もなんとか乗り越えることができるかもしれません。