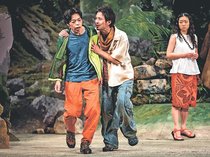――文学館は元々知事公舎で、歴史のある建物です。お気に入りの場所は?
お庭ですよ。文学館の庭はいい。私の父は48歳で亡くなる前、急に花を植え始めたんですよ。若いころの私は「え、急にどうして?」と思ったのですが、いざ自分が年を取ってみると、父の気持ちが分かりますね。 生き物も結構いるんです。

館長室の窓を開けて「ただいま~」と声をかけると、鳥たちがピッピッと鳴いてくれます。実はヘビも住んでいるみたいで、職員が脱皮した皮を見つけたそうなんです。私はまだ本体に遭遇していないので、退職するまでに絶対会いたい(笑)。

――館長就任から3年目を迎えました。
前任の中西進先生は、日本を代表する文学者でしょう? 万葉集の専門家で、世界的にも著名な方です。すごすぎて、最初から「比べてもしょうがないや」という気持ちでした。私が同じようにやろうとしても不可能なので、自分なりのやり方で頑張ろうと思ったんです。
でも、実際に文学館の運営に携わりながらいろいろなものを目にしたり、体験したりしているうちに、少しずつ「あ、なるほど。こういう面白さもあるんだな」と思う瞬間が増えてきました。自然と読書の幅も広がりました。学びながら自分だからこそできることをやろうとしています。
――エッセー集『ゆうべのヒミツ』の中では、文学館の課題を「若返り」と書いていましたね。
言うはやすしで、なかなか難しいですね。いろいろ企画して「これなら若い人が来てくれるかも」と思っても、結局中高年の方が中心になることが多いんです。だからと言って、まったく文学に関係のないYouTuberやタレントを呼んでイベントをするのも違う気がしていて……。これまで文学館を愛してくださった方々を大切にしながら、どうやって若者にとって魅力的な場所にしていくか。まだまだ試行錯誤しているところです。
今は池波正太郎展が開催中です。時代小説の『鬼平犯科帳』シリーズや『剣客商売』シリーズなどはファンが多いので期待しています。男性ファンが多い印象がありますが、奥様たちが「帰りにお茶でも」と連れ立ってお越しいただくにはどうしたらいいかと、頭をひねっています。でもね、人間ドラマの深さが特長の作家さんなので、性別に関係なく楽しんでもらえると思いますよ。

――東京との往復生活ですが、やってみていかがですか。
県庁の方から打診があったときは「本当にできるかな」と不安でした。でも、10年くらい前から富山でラジオ番組を2本やっていて、月に2回は通っていたんですね。北陸新幹線が開業したおかげで、雪の時期でも日帰りだってできてしまいます。移動自体は好きなので、意外と大丈夫でしたね。移動時間に本も結構読めますから。 今は月の3分の1くらいは富山に滞在しています。その間はホテル暮らしなので、ご飯がね、ちょっと悩ましい。最近自転車を買ったんです。暖かくなったらもっと遠出して、お店を開拓したいですね。
――いかにも公務員的な会議や事務仕事はなかなか慣れないのでは。
最初は「何時から何時はこの会議、その後これを確認して…」と細かくスケジュールを組まれて、「はあ、本当に?」と思いましたよ(笑)。聞き慣れない行政用語も多いしね。でも、徹底的に聞き返しています。分からないまま進めるわけにはいかないですから。あと私、意外と数字が好きなんですよ。

数独が趣味で、暗算もわりと得意。予算や経理的な話にもそれほど抵抗はありませんね。もちろん疲れますよ。でも、ドラマや映画の撮影現場は朝から晩までヘトヘトになるほど働きますから。やると決まったらやりきるという点では、俳優と館長の仕事もあまり違いがないかもしれません。
――室井さんならではの取り組みとして、展示に合わせて絵本を作っていますよね。
翁久允展ですね。職員から「子どもでも楽しめる形にできないか」と提案があって書きました。全集を借りて、自分でコピーして読み込みました。昔の富山弁や風景が生々しく描かれていて、意外なほど面白かった。それを自分なりに凝縮してまとめたつもりです。久允さんとは親戚関係にあるので、良い機会でした。こういうことでもないと全集なんて、なかなか読まないからね(笑)。
――井上ひさし展では、開催に合わせて朗読劇をやりましたね。

学芸員さんに朗読用の作品を提案してもらいつつ、最終的には自分で図書館や本屋さんを回って「声に出して舞台映えする」テキストを探しました。文章として素晴らしくても、舞台上でイメージが伝わるものとそうでないものがあるんですよね。学芸員さんも「声に出すと印象が全然違うんですね」と驚いていて、お互い勉強になったと思います。
――今後はどんな構想をお持ちですか。
うちだけの課題ではありませんが、現代作家をどう扱うかは悩ましいところ。昔みたいに手紙やメモが残らないし、プライバシーの問題も厳しい。何を展示して、どう見せるかが本当に難しいんです。でも、そういう時代の流れの中でも文学に興味を持ってもらえる企画を考えたい。