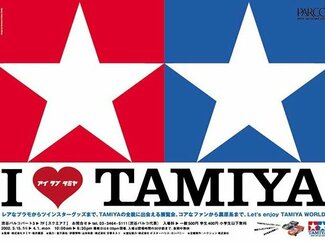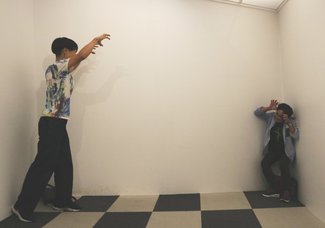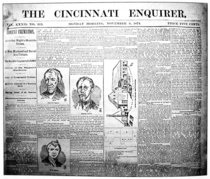本紙文化面の連載企画「たてものに会いにいく」は、県内の建造物を建築家のナビゲーターと巡り、魅力に迫っている。webunプラスでは、ナビゲーター自身の横顔や紙面で書き切れないエピソードを紹介する。第15回は歴史的建造物や景観の再生・活用を手がける文化財修理技術者で建築士、森本英裕さん(41)=富山市。紙面では、自身が修理設計に携わった富山城址公園内の茶室「本丸亭」を紹介してくれた。

事務所で写真に納まる森本さん。棚には日本の伝統建築や茶道に関する本がぎっしりと収納されている=富山市泉町
森本さんは1982年富山市生まれ。建物を見るのが好きで、早稲田大建築学科に進んだ。建築の歴史を学ぶ研究室に所属したことがきっかけで、歴史的建造物に興味を持った。昔の大工が記した古文書を読んだり、古い街並みに出かけて調査したり。同大大学院生だった2008年には、国の「重要伝統的建造物群保存地区」(重伝建地区)登録への機運が高まっていた高岡鋳物発祥の地・高岡市金屋町の調査にも携わった。
学生と共に現場へ
30歳の頃、大工や庭師を養成する職藝学院(富山市東黒牧・大山)の専任講師となり、製図や建築史を教えた。県内の歴史的建造物の修復にも力を注ぎ、本丸亭のほか、富山市宮尾の県民会館分館「内山邸」などの調査、修理設計に関わった。
本丸亭は、明治中期に飛騨高山に建てられた茶室を移築した碌々亭(ろくろくてい)と、2016年に完成した増築棟から成る。
残り1194文字(全文:1809文字)