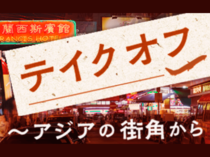低い位置にベースを構え、攻撃的かつダイナミックな低音で楽曲をグイグイとけん引する―。「LUNA SEA」のJが日本を代表するロックベーシストであることに疑問の余地はないだろう。1990年代の彼は、地味な地位に甘んじていたベーシストの在り方を一変させた。
屈指のメロディーメーカーでもある。「ROSIER(ロージア)」は、Jが原曲を作ったバンドの代表曲。居ても立ってもいられないような衝動をかき立てるイントロの核にあるのがJのベースだ。
だが、刊行されたばかりの『MY WAY J自伝』(リットーミュージック)で語られるのは、この曲を作るまでの苦悶の日々だ。疑心暗鬼、不眠、自暴自棄…。この本で「生き地獄」と表現した苦しみの中、Jはどのようにして奇跡の曲をつかみ取ったのか。(取材・文 共同通信=森原龍介)
J 1970年生まれ、神奈川県秦野市出身。1992年「LUNA SEA」のベーシストとしてメジャーデビュー。ソロアーティストとしても活動し、最新のアルバムは「BLAZING NOTES」。雑誌「ベース・マガジン」2025年2月号で、一般投票による「最も偉大なベーシスト」で1位を獲得した。
(1)持て余したエネルギー
●記者 今年2月、結成35周年記念ツアーのファイナルを東京ドームで迎えました。そんな記念すべき年に自伝を刊行して、どんな感慨がありますか。
▼J いろんな節目が重なったタイミングで、この目とこの体で感じてきたリアルな物語を文章に残しておくのは、意味のあることじゃないかなと思っていました。うそみたいな本当の話がたくさんあって、夢物語のような人生をリアルに歩んできたと自分自身でも感じる。夢を見た少年たちが集まってバンドを組んで、天下を取ってやるぞ!って思いで上り詰めていく。もちろん山も谷もあり、いろんなドラマがあった。うまくいった時も、うまくいかなかった時も、最高な時も、本当につらい時も、この本にはぎゅうぎゅうに詰まっている。
●記者 確かにものすごい密度でJさんの原点から今までが語られています。その原点ですが、書店で立ち読みした雑誌に載っていた写真だそうですね。イギリスのパンクバンド「セックス・ピストルズ」のシド・ヴィシャスが鼻血を流しながらベースを弾いている写真だった、と。
▼J 小学校高学年か中学生になる頃だったと思います。あの当時、僕もそれなりにやんちゃな子どもで、自分のエネルギーを持て余していたところ、ロック雑誌を立ち読みして見かけた1枚のグラビアが自分の人生を変えた。僕もロックスターになれるんじゃないかって勇気をくれた。
●記者 音よりまず、ビジュアルだったんですね。
▼J 完全に見た目でした。でも、そこから聴くようになった音楽には、自分の中にたまっているストレスや鬱憤、思いを代弁して叫んでくれたり、でかい音を鳴らしてくれたり、そういったものが詰まっていた。いつの日か自分も…みたいな思いが生まれていったんです。
●記者 お姉さんが持っていたベースにこっそり触れたこともあったとか。弾いてみて自分に合うと思いましたか?
▼J バンドを組もうという時に、僕もギターをやりたかったんですけど、「ギターやりたいやつ」って聞いたら、みんな手を挙げちゃったんですよね。「じゃあ、俺ベースやるよ」って。実はその時はギターとベースの違いが分かってなかった。ただ僕自身、声が低いじゃないですか。ベースっていう楽器に違和感を抱かなかったんですよね。スーッと自分のそばに入り込んできてくれた。
●記者 とはいえ、世間一般のベーシスト像には満足していなかったようですね。
▼J ベーシストは後ろの方にいるちょっと地味な存在で、決まりでもあるのかっていうぐらい目立たない存在だった。僕がベースを弾いたらこうするのにな、ああするのにな、みたいなことばっかり考えてましたね。
(2)郊外から目指した東京のど真ん中
●記者 中学時代、ギターのINORANさんと出会います。高校時代には隣の高校でバンドをやっていた1学年上のギターのSUGIZOさんとドラムの真矢さんを知り、やがて東京郊外の町田のライブハウスに出演するようになる。そこで出会ったのがボーカルのRYUICHIさんでした。5人での初のライブが1989年5月29日。町田という郊外からトップを目指したというのはバンドにとっても大きかったのではないでしょうか。
▼J 僕らが育ったのは神奈川なんですけど、一番近い東京が町田でした。町田の「プレイハウス」というライブハウスでLUNA SEAはスタートしたんです。町田にいたからこそ、ど真ん中で起きていることを冷静に、俺たちだったらこうするのにな、みたいに俯瞰して見ることができた。1日でも早く東京のど真ん中に行きたかったけど、ふとわれに返ると、この町田で何も起きてない。だからここで何かを積み上げて、作り上げてからでも遅くないと感じたんですよね。
●記者 ファンが真っ黒な服で集まる「黒服限定GIG(ライブ)」も町田で始めました。今年2月の東京ドーム公演も「黒服限定GIG」でした。私も黒い服を着て行きましたが、アリーナもスタンドも「SLAVE」(ファン)で真っ黒になって壮観でした。
▼J いつの日か俺たちがでかくなって、東京ドームでこの「黒服限定GIG」をやったらすごいクールだよねって言ってた。それを実現させた一夜ですよね。
(3)ライブの熱を「永遠」に
●記者 Jさんはこの自伝で、自分がベーシストである以上に、ソングライターである意識も強いと語っています。メジャーデビューアルバム「IMAGE」に収録された「WISH」という、ファンに愛され続ける1曲を書いたことは、ソングライターとしても大きな手応えになったのではないでしょうか。この曲は今もライブ最終盤の定番ですが、どんな気持ちで演奏してきましたか。
▼J 目の前にいるファンのみんなとメンバーとで会場に集めた熱を、どうにかして次につなげていく、永遠にしてしまうような曲を、という思いだけで作ったのが「WISH」なんです。僕自身の願いが通じてくれたのかなと思う時もあるし、いまだにその思いがどんどんどんどん膨れ上がって、大きくなっていってるので、うれしいですよね。
●記者 今年2月の東京ドーム、「WISH」のイントロで、真っ黒な会場に一斉に銀テープが放たれて、昔から変わらない演出ですが、きれいな光景だなと思いましたね。
▼J そうですね、ありがたいですね。
(4)積み重ねてきたものが崩れ
●記者 自伝では、1993年にアルバム「EDEN」を出した後、とても苦しい時期があったと明かしています。自分の満足のいく曲が書けない。期待を過度に背負い込む姿に胸が痛みました。人を信じられなくなり、お酒を飲んでも眠れず、追い詰められていきます。最終的にはすべてをシャットダウンして自室にこもりきりになり、心療内科にも通われたそうです。バンドを辞めざるを得ないような状況でした。
▼J 好きだからこそ、自分の思い、焦りがあり、プレッシャーを生んでいき、壁にぶつかる。ものを作っていく上で、やっぱりそういうことってありますからね。ただ、あの当時の苦しさが、自分とは何かをあらためて考えさせるきっかけになったと思うんですよね。
●記者 自伝では、自分の弱さと向き合ったこと、弱さを表に出せるようになったことが大きかったと語っています。グランジなど90年代の内省的な音楽の影響もあったようです。
▼J 本当にとんでもない日々を過ごしたんですけど、自分自身が楽器を持つ前、音楽を始めた頃の気持ちに戻ることができた。音楽をやることって別に理由なんかいらなくて、ただ「やりたい」ってだけで良かったのに、いろんな理屈が必要になって、評価されることに対しても臆病になったり、不安になったり、影響されたり…。だけど音楽は自分の心の中にずっとあるものだって気づいた瞬間だったんだろうな。積み重ねてきたものが崩れて、ゼロからまたスタートできた。それが「ROSIER」を作る原動力になった。あの時に感じたことは、今でも鮮明に覚えてます。評価もセールスもどうでもいい。自分がかっこいいと思うもの、自分が本当に熱くなれるもの、その思いに忠実になろうと作ったんです。
(5)5人で響かせる
●記者 「ROSIER」は1990年代という憂鬱な時代の空気を切り裂くような曲でした。Jさん自身による英語の語り「I am the trigger(俺は引き金)」も印象的です。
▼J 無欲で作った曲がみんなの心の中に今でも響いてくれてると思うと、音楽っていうのは本当にすごいものなんだとあらためて感じます。気がつけば30年前の曲なんですよ。いまだにみんなが好きでいてくれるのは、作った人間としてはとんでもなく光栄なことです。
●記者 疾走感のある長いイントロ、サビがずっと続くような構成、後半に向けてスピードを上げてさらにうねりを増す展開、さまざまなアイデアを詰め込んで作った曲だと語っています。
▼J でも、理屈じゃないんですよ。当時はタイアップ全盛の時代で、売れる曲のフォーマットが出来上がってシステマチックになってきた時代でもありました。でも、僕らはそういうところから始まっていない。「ROSIER」はイントロの長さもサビの回数もフォーマットからかけ離れていましたし、ただ、そういう要素が他にはないスリルや感情の爆発を誘うようなエネルギーを生んでるのも事実だし、そういう意味で何にも邪魔されないで作った曲ですね。次のシングル「TRUE BLUE」でタイアップなしで1位を取った。こういうタイアップなら必ずヒットチャート1位を取れるはず、というふうに各社が動いていた時代なので、売れ線のバンドの人たちにレコード会社の人たちは相当怒られたっぽいですよ(笑)。
●記者 ところで活動初期のアルバムでは、作詞は誰、作曲は誰と明記されていましたが、メジャーデビュー後はバンドの共作と表記するようになりました。
▼J バンドの曲っていうのは、イニシアチブを握る人間がいたとしても、やはりそれぞれのパートが最高の状態で、熱が最大限に入ってこないと、一番いい輝きをしない。そういう意味で、みんなで作る、みんなで響かせるイメージなんですよね。「その方がもめないからね」とか言われるんですけど、そういう理由では全くないんです。
●記者 確かに、「ROSIER」はJさんが持ってきた曲で、ベースとドラムのシンコペーション(リズムの変化)が性急なスピード感を演出していますが、RYUICHIさんのボーカルはもちろん、INORANさんの歯切れのいいギター、SUGIZOさんの美しくヒステリックなソロ、加速していくドラムとそれぞれに見せ場があり、全員野球でクライマックスへとなだれ込みます。バンド運営も合議制だと聞きますが、バラバラの個性を持っている5人なのに一体感があるのが魅力です。
▼J みんなが100%の力を注ぐことを前提としているバンドで、メンバーそれぞれがリーダーシップを取れる。だからこそ、ずっとバンドのフィロソフィー、哲学として合議制でした。誰かがノーだったら、多分やらないでしょうし。
(6)究極のベースフレーズ
●記者 ベースプレイで言うと、1995年の「DESIRE」、1996年の「END OF SORROW」でのJさんのスライド奏法はかっこよかったですね。弦を抑える左手をダイナミックに横に滑らせて派手に音をうねらせるJさんのスライドですが、どのように自分の武器にされたのでしょうか。
▼J フレーズとフレーズをつなぐスライドとかグリス(グリッサンド)という奏法はベースという楽器の醍醐味でもあります。でも、かっこいいスライドもあれば、もうちょっとダイナミックでもいいんじゃない?みたいに感じるものもあって、センスを問われる奏法なんです。バンドを始めた頃、ベーシストには個性的な先輩がたくさんいて、僕が入っていける余地がないと思っていたんです。僕の売りってなんだろう?って。僕はそんなにうまく弾けないし、うまいフレーズも作れない。だったら、フレーズを全部つないじゃおうって思ったんです。そしたら、これって俺しかやってないんじゃないか?って。音を細かく刻まなくてもベースのフレーズは作れると思って、それから自分自身のスタイルとして極めていきました。「DESIRE」「END OF SORROW」は、自分でもスライドを絡ませた究極のベースフレーズだと思いますね。
(7)あらがうものがなくなった
●記者 1995年には、東京ドームで「LUNATIC TOKYO」という伝説的なライブを開催します。ただ、自伝を読んでいると,この頃から、2000年の「終幕」に向けてだんだんとバンドの熱が冷えていくように感じました。
▼J 今思い返すと、僕たちは東京ドームでプレイすることを一つの目標にしていましたし、ライブが終わった後、それぞれが「さぁここからどうしよう」っていう思いになっていた。さらに上に行くとしても、どういう道で、どういうアプローチをしていくのかはそれぞれのメンバーに表現の仕方がある。もっと言うと、今まではロックバンドとして何かにあらがっていれば成立していたものが、僕らがメインストリームになってしまったことも大きかった。
●記者 1995年以降もライブの規模は大きくなる一方でした。1999年、野外で10万人を集めた「NEVER SOLD OUT CAPACITY∞」を開きます。開催直前に突風に見舞われ、崩壊したセットの中でライブをするというドラマチックな展開です。でもそういう劇的なストーリーにしか活路がなかったようにも思えます。
▼J そうですね。誰もが通ってない道を通るというのが僕たちのフィロソフィーだったんですけど、誰も見たことのない世界には相当なエネルギーを使う。家族より長い時間、大の大人が一緒にいるわけですから、いい時もあれば悪い時も当然ある。その中で一緒に音楽をプレイしていく意味、してきた事実、いろんなことを自分たちで受け入れて、バンドとして吐き出していかなければいけない。そのためにはバンドとして時間が必要だった。そういうタイミングだったんだろうなと思うんですね。
●記者 96年末にいったんバンド活動を休止して、各自が1年間のソロ活動をする。再びバンドに戻りますが、結果として2000年末で「終幕」を迎えます。その後、長い空白の期間を経て2010年に「REBOOT(再始動)」しますが、今になって振り返ると空白の時間も必要だったということでしょうか。
▼J そう考えられる場所まで僕らはたどり着けたのかなって思うんです。当時はもう無理だ、ここまでだ、と思っていましたからね。
(8)この瞬間は今しかない
▼J 若かった頃と今と、時間の速度は一緒ですけど、時間の意味が変わってくる。俺たちはいつまでできるんだろう。周りでも悲しいお別れやいろいろな経験がある。永遠じゃないんだ…て思う。だからこそ、永遠ってものを作ってみたいっていうのは、今、本当に強く感じるんですよね。
●記者 メンバーはそれぞれに年齢を重ね、特にRYUICHIさんは病気もなさって以前と同じような歌声という訳にはいかないのかもしれません。でも歌う。その姿にグッときました。Jさんは演奏しながらどう感じましたか?
▼J 彼自身、病気になって喉のコンディションと闘っていましたからね。ずっと同じバンドをやってきたからこそ、彼が向き合っているもののデカさも感じていた。僕らが手を差し伸べて、何かが変わるものでもない。ただ、それは誰にだって起こること。僕らもそういう歳になったってことだし、もっと言うと、ライブに来てくれた皆さんもそうじゃないですか。この瞬間は今しかない。僕らも含め、みんなでその瞬間に一緒になって、何もかも忘れて最高な時間を過ごして盛り上がれる。これは本当に特別なことなんだ。これからも可能な限り、みんなで一緒に燃え上がっていけたらいいなって思いますよね。
(9)世代の責任
●記者 若い世代もLUNA SEAを聴いています。この本の中では、ご自身の世代の「責任」という言葉も使いました。
▼J 責任というのはロックとは正反対の言葉のようですが、僕らの音楽を聴いて、影響を受けて、今この日本の音楽シーンで最前線を突っ走ってるやつらをたくさん知ってますし、俺たち5人がしっかりしないといけないって常に思っている。
●記者 11月8、9日にはLUNA SEAが主催する大規模なイベント「LUNATIC FEST.」が千葉市の幕張メッセで開催されます。櫻井敦司さんを亡くした「BUCK-TICK」、「黒夢」といった同時代を駆け抜けたバンドだけでなく、「UVERworld」「My First Story」といった後輩のバンドも駆けつけます。
▼J 僕らはバンド人生で、アナログからデジタルへの移り変わりを全て見てきて、上の世代と下の世代をつないでいける最後のポジションにいるんじゃないかと感じていたんですね。それがルナフェスの熱の真ん中にある思い。その熱量のすごさを次の世代につないで、上の世代にも若いやつらの熱を伝えて循環させることができたら、俺たちにしかできないとんでもないフェスになるよね、なんて話から始まったんです。今回もとんでもない2日間になると思う。ぜひ皆さん遊びに来てほしいですね。