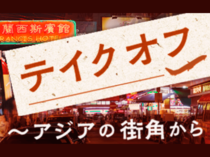真夏の夜、東京・千駄ケ谷の国立能楽堂で「船弁慶(ふなべんけい)」を鑑賞した。義経と弁慶、静御前に平知盛と、いわばこの時代のスターが繰り広げる劇的な演目だ。能を見るたびに自問する。舞台上の一つ一つの瞬間から私は何を感じ取れるのか。自らを試すようでもあり、胸が高まる時間でもある。
「船弁慶」の前半、西国に向かう義経一行に同道していた静御前が泣く泣く都に戻ることとなり、別れの前に舞を披露する。愛する義経との再会を願う心を表すのは優美な舞と能面の動きである。
観世流シテ方遠藤喜久がかすかに面を伏せると、静御前の心が震えていることが感じられる。客席で見る側の気持ちも、面が上下するたびに変化していく。張り詰めた空気の中で所作を凝視した。
後半、シテは静御前から一転して平家屈指の勇将とされる平知盛の霊を演じ、義経たちが乗る船に襲いかかる。小鼓、大鼓などが激しく鳴り響き、嵐の大波を想起させた。
簡素な能舞台は死者と生者の境遇を再現する空間となる。あるときはこまやかな心情の移ろい、ある時は勇壮に振り下ろされる刃の軌跡。見えるもの、見えざるものが交差する。
高まる緊張の中で、一つの思いが浮かんできた。私たちは感じる力を試されているのではなく、この場にいる観客を含めた誰もが、死者の無念や生者の執着を共に感じるよう求められているのではないか。空間を切り裂く笛や身体に幽玄を宿らせる舞、押し寄せる地謡の声と囃子のそれぞれに身を浸す。
「船弁慶」は、分かりやすさもあって人気の曲といわれる。私が見たのは国立能楽堂が企画する「ショーケース」の公演の一つ。狂言と能を鑑賞する入門編のプログラムで、能楽師が作品を解説するプレトークもある。
正直に言えば、私にとって能、狂言のハードルはなかなかに高いのだが、国立能楽堂では座席の字幕と解説の画面に助けられ、せりふや地謡の抑揚、緩急が耳になじみやすい。
同じショーケースの企画で別の日に演じられた「葵上(あおいのうえ)」でも、観客の想像力を喚起する演出を味わった。「源氏物語」に材を取った演目の冒頭、舞台に一枚の小袖が置かれる。これを病床に伏せた葵の上と見立てて舞台は進む。
前半では、光源氏の愛情を得られなくなった六条御息所の生霊(観世流シテ方柴田稔)が嫉妬心をたかぶらせ、病の床にある葵の上、つまり小袖を打ち据える。後半、六条御息所の生霊は鬼と化す。相対する名高い修験者は数珠をもんで一心に祈り、迫り来る地謡と囃子もまた、両者の戦いの激しさを描く。ついに生霊は敗れ悪心は清められた。
板張りの舞台に伸べた小袖を人そのものと感じ、鬼の面をただ恐ろしいもので済ませるのではなく、その奥にある悲しさに思いを巡らせる。余韻を残す静寂の中、小袖は最後に畳まれて舞台を去った。
宮本亜門監督の映画「生きがい IKIGAI」では、主演の鹿賀丈史が実に深い表情を見せている。石川県・能登の土砂災害で崩れた家の下から救出された元教師は、地元で「黒鬼」と呼ばれていた。しかし、人を遠ざける険しい表情の奥には、ある思い出が宿っている。
黒鬼の顔に何が凝縮されているのか。演者が込める深い心情を、見る者がどれほどつかみ取れるのか。この作品でも能の演目のように共に感じることを求められていると思う。黒鬼の目の光に少しずつ変化がきざす。短編ゆえの鋭さに感じ入った。北陸能登復興支援を掲げる作品。
表現の背後や奥底をつかむ感覚を身につける近道はないかもしれないが、頭の隅に「もっと面白く」「もっと知ろう」という意識を置いていたい。(杉本新・共同通信文化部記者)
【今回の作品リスト】
▽国立能楽堂ショーケースから「船弁慶」「葵上」
▽映画「生きがい IKIGAI」(宮本亜門監督)