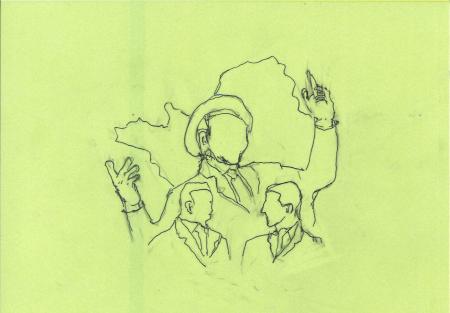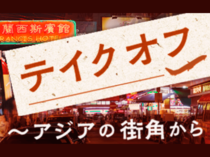2014年にノーベル文学賞を受けたフランスの作家パトリック・モディアノ(1945~)の初期3部作はいずれも、1940年から1944年にかけてフランスがドイツに占領されていた時期を背景に展開する。モディアノは20代の前半に『エトワール広場』(1968年)で華々しくデビューし、次作『夜のロンド』(1969年)、第3作『パリ環状通り』(1972年)=アカデミー・フランセーズ小説大賞=と書き継いだ。彼はこれらの小説で、自分が生まれる直前の不安で混乱した世界をのぞき込み、そこにうごめく謎めいた人々を造形した。作中に書き入れられたさまざまな音楽が、薄暗くかすむ時代の彼方から聞こえてくる。
モディアノの著作は数多く翻訳され、熱心な読者がついているようだが、誰もが知る名前ではないかもしれない。まずは人物像を側面から紹介させてもらおう。
彼は若いころ、シャンソンの作詞を手がけたことがある。代表作は人気歌手のフランソワーズ・アルディに提供した『驚かせてよ、ブノワ』(エトネ・モワ・ブノワ)。1968年発売のアルバム『さよならを教えて』に収録されている。
映画にも関わり、ルイ・マル監督の『ルシアンの青春』(1974年)では、監督と共同で脚本を書いた。主人公はレジスタンスに加わりたいと考えていながら対独協力者になった少年である。マルはロング・インタビュー集『マル・オン・マル』(キネマ旬報社、平井ゆかり訳)でこう述べた。「彼(モディアノ)のデビュー作の二つはドイツ軍占領時代の末期を舞台にした対独協力についての小説で、私はとても気に入っていた。私はこの時代に特別な想いを寄せるこの小説家といつか一緒に仕事をしなければならないと思っていたし、事実彼は、このシナリオのユダヤ人家庭の描写部分には大いに力を貸してくれた」
映像作品との関連では、作家本人もびっくりしただろう事実がある。記憶の喪失と回復を扱ったゴンクール賞受賞作『暗いブティック通り』(1978年)が、一世を風靡した韓流ドラマ『冬のソナタ』に影響を与えていたのだという。後者の脚本を担当したキム・ウニ、ユン・ウンギョンの共著『もうひとつの冬のソナタ』(ワニブックス、うらかわひろこ訳)には、次のように書かれている。「シナリオを書いていたころにはまったく気付かなかったことですが、後でじっくり考えてみたら私たちふたりが共通して好きな小説がひとつあったのです。フランスの作家で、パトリック・モディアノという人が書いた『暗いブティック通り』という小説です」。無意識のうちにかもしれないが、2人はこの本から学んで『冬ソナ』を書いていた。「とくに主人公のチュンサンが記憶を失い、またそれを取り戻していく過程でのチュンサンとユジンの心理を描写する時、今考えると、とても参考になったと思います」
『暗いブティック通り』の日本語版(平岡篤頼訳)は最初、1979年に講談社から刊行された。2005年に白水社から改めて出たのは、前年に『もうひとつの冬のソナタ』が邦訳され、『冬ソナ』との関係が知られたことにもよるようだ。白水社版のあとがきで平岡は「以上のような相似点に興味を持って、モディアノのこの秀作を再び世に問うのも(便乗というそしりは免れないとしても)無駄ではないと考えたというわけである」と言い添えている。
美術についても付け加えることがひとつある。モディアノ作品によく名前の出るエコール・ド・パリの画家アメデオ・モディリアニは彼の遠縁にあたるそうだ。モディアノ自身がノーベル賞の受賞スピーチで明らかにしている。
さて、これでモディアノという作家にだいぶ親近感が増したのではないだろうか。そろそろ3部作のそれぞれについて見ていきたい。
『エトワール広場』と『夜のロンド』は作品社から1冊になって出ている(ともに有田英也訳)。さらに別綴じで、計76頁に及ぶ関連地図、解説、訳注が訳者によって付されている。私を含め、大方の現代日本人は占領下のフランスについてよく知らないと思うので、この付録はきわめて有益だ。
『エトワール広場』の冒頭は、語り手ラファエル・シュレミロヴィッチの「それはわたしがベネズエラの遺産を食いつぶしていた頃のことだった」という言葉で動き始める。相続した遺産は、かの国にいた伯父のものである。ラファエルは挑発的な文書をいくつか発表し、若くして一種のセレブにもなっていたが、「一九四〇年六月。(中略)わたしはジャーナリズムに飽きて、政治的野心を暖めている。対独協力ユダヤ人になる決心をしたのだ」という思いに突き動かされる。1940年はパリがドイツに占領され、ヴィシーにペタン元帥を主席とする傀儡政権ができた年である。
忘れないうちに言っておかなければならないが、この小説の叙述は直線的に進行するのではない。時間も土地もばらばらな挿話がつなぎ合わされ、万華鏡のように変転を繰り返していく。さらに、個々のエピソードの中でも時と所のねじれがある。次はその一例。
伯父の遺産を受け継いだラファエルは、アメリカにいる父に「三五万ドル相続する気があるなら会いにこい」と呼びかけた。父は1944年7月にフォンテーヌブローの森をドイツ人に売り飛ばし、その金でアメリカに移住した。それから何年も経っていたと思われるので、相続の誘いは戦後であるはずだ。しかし、読み進めると、実際にいつのことだったか不明確になっていく。
パリで再会した親子はボルドーへ行く。すると、時間が大きく巻き戻されたのか、ラファエルは当地のリセ(中等教育課程の公立学校)の高等文化クラスに登録する。この旅の時、ホテルへ向かうタクシーの中でラファエルが父に「きっと運転手はフランス人ゲシュタポの一味だよ」とささやく。すると、車は占領下のパリを走りだす。今度は1940年代前半へのタイムスリップである。しばらくすると舞台は再びボルドーに戻る。「午前零時。わたしは部屋の窓を半開きにする。この夏のヒット曲、ストレンジャー・オン・ザ・ショアーがここまで聞こえてくる」。ラファエルが名前を挙げた楽曲は邦題を『白い渚のブルース』といい、1960年代の初めにヒットしたムードミュージックである。
これでボルドー行きの時期がはっきりした、と言いたいところだが、モディアノがこの曲で年代を示唆したかったのかどうかは疑問である。フランスに住むユダヤ人であるラファエルを<ストレンジャー>と位置づけ、そこにボルドーが川沿いの土地であることを重ね、<岸辺の異邦人>を意味するこの曲の題名を借りたと考えてもおかしくはないだろう。ちなみに、ラファエルは本作の始めの方で「わたしはオリエントの祖先から、黒い瞳と、自己顕示欲と奢侈への好み、不治の怠惰を受け継いでいる。わたしは地元の子ではない」と述べている。
ラファエルはリセで問題を起こして退学し、たまたま出会った男によって国際的な売春組織に組み入れられるが、その部分は端折ることにする。
万華鏡が何度かひねられ、ラファエルはウィーンにいる。カフェで知り合った女がジュークボックスにコインを入れた。「すぐにツァラー・レアンダーの声が、しゃがれた甘い河のように、わたしを揺すぶる。彼女はイッヒ・シュテーエ・イン・レーゲンと歌っている。私は雨の中を待っている。ミット・ローテン・ローゼン・フェンクト・ディー・リーベ・マイステンス・アンと歌う。恋はいつも赤いバラから始まる」。モディアノはこれを受けて「恋はしばしばジレット・エクストラ=ブルーのカミソリの刃で終わるのだ」と書く。<恋><赤><青>の連想で歌詞と地の文が繋がっていくのだが、最後の一句には、ラファエルの恋人の一人がかつて、静脈を切って自殺していたことが重ねられているだろう。
レアンダーはスウェーデン出身の女優・歌手で、ナチス時代のドイツ映画に主演してスターになった。女性としては極めて低い声域で、1回聴くと忘れられない。この時ジュークボックスで流れた最初の曲は映画『世界の涯てに』(1937年)の挿入歌。二番目は戦後の1956年に歌った曲である。
あいまいな繋がりの連続なので経緯は省くが、ラファエルはウィーンの警察によってイスラエルに送られ、身柄を拘束される。しかし、ある女性中尉が彼を気に入り、<ツァラー・レアンダーとマレーネ・ディートリヒの歌に合わせてダンスのできる非合法ナイトクラブ>に連れて行く。クラブは陸軍の若い女性に大人気で、パートナーは入口でドイツ空軍の軍服に着替えなければならないというから、倒錯の限りを尽くしている。
「彼ら(ラファエルと女性中尉)の最初のダンス曲は『風がわたしに歌を聴かせた』と歌うタンゴだった」。映画『南の誘惑』(1937年 原題La Habanera)でレアンダーが歌った曲である。レアンダーの歌がもう1曲続いたあとには、ララ・アンデルセンの『リリー・マルレーン』。大戦中、レアンダーはドイツに招かれて名を挙げ、ディートリヒは反ナチスを貫いた。アンデルセンの『リリー・マルレーン』は敵味方の別なく愛唱された歌として知られる。3人の中で比較するなら現在の知名度は高くないレアンダーだが、『エトワール広場』ではドイツとの親密な関係ゆえに一番重要な役を振られている。
物語はまだ少し続くが、幻想に次ぐ幻想に長くさまよったので、このあたりで次の『夜のロンド』に移ることにする。
語り手の<わたし>は元捜査官のフェリベールやフランス人ゲシュタポのル・ケディヴを中心とした<私設警察もどき>と関わり合いになり、レジスタンス組織の内偵をさせられる。この時彼に与えられた登録名が<スウィング・トルバドゥール>。シャンソン歌手で作詞・作曲家のシャルル・トレネ(1913~2001)が1941年に発表した歌の題名である。
<トゥルバドゥール>は中世の南仏で宮廷を遍歴した抒情詩人。この歌の主人公はスウィング・ジャズ時代の吟遊詩人に擬せられているわけだが、恋人がどこかへ立ち去ってしまったために「かわいそうなスウィング・トルバドゥール」という句が繰り返される。語り手の将来も明るくはなさそうだ。
そして私が思うに、<スウィング>の方には何か別の意味が隠されているのではないだろうか。少し先回りすることになるが、語り手は警察もどきとレジスタンス組織の間で心ならずも二重スパイのような役回りになる。態度が揺れ動く(スウィングする)ことがコードネームで予言されていると考えるのは、深読みにすぎるかもしれないが、個人的には捨てきれない。
ここで一息入れて、トレネの代表曲を紹介しておこう。『詩人の魂』『ラ・メール』のメロディーは多くの人がどこかで耳にしていると思う。シャンソンの名曲を集めたアルバムには必ずと言っていいほど入っているはずだ。『アイ・ウィッシュ・ユー・ラヴ』という題でジャズ・スタンダードになった『残されし恋には(ク・レスト・ティル・ド・ノ・ザムール)』も忘れてはならない。トレネ本人をはじめさまざまな人の歌唱で親しまれるが、英語版で言えば、ナット・キング・コール、フランク・シナトラから、ナンシー・ウィルソン、バーブラ・ストライサンド、チャカ・カーンに至る名歌手たちがこぞって取り上げている。元がシャンソンだと知らないジャズ・ファンもかなりいるのではないか。
さて小説の冒頭、フィリベールたちは屋敷の広間に集まり、レジスタンス組織の摘発や商売の話をしている。仲間の一人が「俺たちにはスローな曲が必要だ」と言い、グレタ・ケラー(ウィーン生まれのキャバレー歌手)のレコードをかけてタンゴを踊る。ダンス好きらしい女性がもっと踊りたいといい、ほかの面々に好きな曲を言わせる。名前が挙がったのはノロ・モラレスの『セレナータ・リトミカ』、ティト・プエンテの『ココ・セコ』といったラテン音楽、ミュージカルやオペレッタの劇中歌などだ。『ノ・メ・デヘス・デ・クエレル』はよく分からない。モディアノは年代の整合性を重視しない作家だが、さすがにグロリア・エステファンが2000年にヒットさせた曲ということはありえない(『夜のロンド』の発表は1969年)。おそらく同じ題で別の曲があったのだろう。
この小説では時々、歌詞の断片と短い地の文が交互に現れる。警察もどきの中のひとりがヴァイオリンを弾きながら『恋なんかでもう泣かないわ』(これもツァラー・レアンダーの曲)を歌う場面もその一つ。「恋なんかで…」「地球の上には…」「この世界に…」「男はひとりじゃないし…」と続いていく歌詞と歌詞の間に、最初は歌っている男の描写、それに続いて語り手が子供のころ、メリーゴーラウンド(「だんだん速度を上げる無限軌道」)に乗ると必ず怖がったことが述べられる。メリーゴーラウンドは動き出したら途中で降りられない。自分ではどうにもならない運命の比喩だろうか。「そしてあなたに愛を誓う…」「わたしは誰でも好きになるの…」「わたしは嘘をつくわ…」のあたりでは再び歌い手の様子を写すが、それにはあまり意味がないと思う。おそらく、語り手が警察もどきとレジスタンス組織の間に挟まれ、どちらにつこうか迷っていることに関係しているのだろう。
歌の方の『スウィング・トルバドゥール』が出てくるのは、語り手が警察もどきの側に立たざるを得なくなり、レジスタンスのリーダーたちをだましてカフェにおびき出す時である。彼らがやってくる前、カフェの蓄音機でこの曲が鳴る。「けれども君の女友達は旅行中 かわいそうなスウィング・トルバドゥール」「かわいそうなスウィング・トルバドゥール かわいそうなスウィング・トルバドゥール」。繋がりをよくするためだと思うが、1920年代にベルト・シルヴァが歌った『不良の心』の一節「そして春のバラを摘んで悲しそうに花束にした」が中間に挟み込まれている。
少し飛ばして先へ行くと、語り手はバーテンダーになっていて、ここでも『スウィング・トルバドゥール』がかけられる。「すべて終わった。もう散歩もない もう春は来ない、スウィング・トルバドゥール」
本作に書き込まれたトレネの歌にはこのほか『今晩は、美しいマダム』『残されし恋には』『ラ・メール』『青い花』『母さん、家を売らないで』がある。若い頃にトレネがコンビを組んでいたジョニー・エスとの歌『いつかいい天気になったら』から取られた「街は大きなメリーゴーラウンドのようなもの/ひと回りするたびに/ぼくたちは少しずつ老けてゆく…」は、子供のころメリーゴーラウンドを怖がった語り手の思い出とうまく響き合っている。
申し遅れたが、トレネの歌は『エトワール広場』でも、『フォルミダブル』(最高さ)や『僕のミュージック・ホール』の歌詞が引用されていた。ここで補足しておく。
3部作の最後にあたる『パリ環状通り』(講談社刊 野村圭介訳)は前2作に比べ、割合に筋が見えやすい。ただしちょっとした仕掛けはある。
登場人物はみな怪しげだ。最初のシーンでは、いかがわしい週間新聞を出しているミュラーユ、外人部隊上がりのマルシュレ、<小修道院>と呼ばれる邸宅にすむ正体のはっきりしない男デックケールの3人が、フォンテーヌブローの森のはずれにあるホテル<クロ・フクレ>のバーに集まっている。ホテルの支配人である女性モー・ガラも部屋の奥にいる。「三人の男たちとモー・ガラのぼんやりしたシルエットをよく見れば、この場面は、はるかな過去のものだと思われる」と、それに続く「偶然引き出しの奥から発見され、丁寧にほこりをふきとった一葉の古い写真。日が暮れる。亡霊たちは、いつものようにクロ・フクレのバーに入った」を読めば、彼らが写真の中の人物であり、それを見ている語り手の心の中で生命が与えられ、動き出す小説であることがわかる。いつの話であるかは「事態の憂慮すべき成り行き」「この混迷した時代」「今日のような悲劇的な時代」「こんな世の中だから」「実に困難な時代」「未曾有の価値混乱の今日」と、そのつど表現を変えながら繰り返し出てくる言葉で判断すればいいだろう。
語り手もその写真の中の世界に入っていく。彼はデックケールが自分の父であると知っているが、それを口にすることはない。父の方では息子が識別できない。モディアノは本書の序文で「作者は、同世代の多くの若い人々が感じる、『父』の喪失による不安や心配を、語り手の青年と共に生きようとした」と書いている。
それではもどかしい<父親探し>の物語に、音楽はどう絡んでいくのだろうか。ミュラーユたちが集まっている屋敷のベランダで、語り手と父がとりとめのない話をしていた時を例にとろう。
「サロンからは、しわがれた声で歌うタンゴのひとふしが聞こえてきた」という印象的な文に続き、歌詞の断片<ランプの灯のもと…>が引用される。この曲は、タンゴの歴史で最も重要な歌手とみなされているカルロス・ガルデルの<A la Luz del Candil>だ。語り手は父を誘って庭に出る前、ガラス戸の方を一瞥する。「ガラスには水蒸気がかかり、黄色いもやの奥に、ぼんやりとした三つの大きなしみが見えるだけだ」。彼が目にしている幻影の世界は、ランプの淡い光に照らし出されたようにぼおっと見えるのだ。
もう一度「ランプの灯のもと…」が繰り返され、語り手は「きれぎれに聞こえてきたタンゴの響に私は当惑した。ここは本当にセーヌ・エ・マルヌ(彼らのいる県の名前)なのだろうか? ひょっとしたらどこか熱帯の国にいるのではないだろうか? サン・サルバドルとかバイア・ブランカとか…」と考えを巡らす。彼はきっと自分がどこにいるのか分からない不安に襲われたのだろう。
後に語り手は、父がどんな人間だか少しも分からなかったと言う。「私はあなたについて何もしらない。まるで、ほの暗いランプのもとの、かすかにそれとわかるひとつの影」
モディアノは序文でこうも言っている。「『パリ環状通り』は、不安と混乱の雰囲気(アトモスフェール)、たそがれ時の漠とした情調を持つ作品であり(後略)」。その<漠とした情調>にふさわしい曲が、小説の最後の方に出てくる。語り手と父がパリのシャトレ広場にある軽食堂に入った時、ピアニストが弾いていた『我が夢の館』である。ギタリストのジャンゴ・ラインハルトが作った名曲の一つで、題名はマクトーブ別荘や父の邸宅を想起させる。いずれにせよ、それらはすべて夢だったのだ。(松本泰樹 共同通信記者)
まつもと・やすき 1955年信州生まれ。3年と少し続いてきたこの連載は、次回が最後になる。理屈っぽかったり、ひとりよがりだったりする文章を読んでくださった方々にお礼を申し上げたい。本当にありがとうございました。頭の中にはテーマがまだまだ多く眠っている。最終回ではそれらのうちのいくつかを、ほんの少しずつご覧にいれましょう。