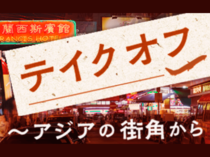戦後80年の今夏、作家の大田洋子(1903~63年)による原爆文学2作を収録する「屍の街・夕凪の街と人と」(岩波文庫)が出版された。巻末のかなり長い「解説」を書いたのは、若き日に大田の評伝「草饐(くさずえ)」(1971年)を著したノンフィクション作家の江刺昭子(1942年~)、大田文学研究の第一人者だ。江刺や、広島で活動を続けてきた市民団体「広島文学資料保全の会」の存在がなければ、この不遇の作家の手による原爆文学は、歴史の闇に埋もれていたかもしれないとさえ思う。
「屍の街」など大田の作品は絶版状態が長く、いつの間にか知名度がかなり低い作家となってしまった。江刺は解説の中で「原爆問題を中心テーマにした大きな文学に挑戦し、『原爆文学』というジャンルの確立に力を尽くした大田洋子という作家がいたことを記憶してほしい」と記している。
なお、「屍の街」や「夕凪の街と人と」を小説と見ない向きもあるようだが、私はルポルタージュふうの小説だと判断している。
■後世に残すべき作品
「屍の街」は、原民喜(1905~51年)の「夏の花」とほぼ同時期に書かれた作品で、原爆小説の嚆矢である。脱稿は1945年11月と思われるが、出版は作家の思うようには進まなかった。
江刺の綿密な調査によれば、大田が雑誌「中央公論」の編集部に「屍の街」の原稿を送ったのは1946年初めだった。それを読んだ編集者は「後世に残すべき作品」だと思うが、編集長がプレスコード下での掲載は難しいと判断し、見送られる。
プレスコードは連合国軍総司令部(GHQ)が1945年9月下旬に発布、新聞や出版に対し、連合国や進駐軍に関する「破壊的批評」「不信または怨恨を招くような記事」などを禁じていた。
結局、中央公論社(当時)から「屍の街」が出版されるのは、脱稿から3年を経た1948年11月。だが、出版社側の自主規制で「無慾顔貌」の章が丸々削られてしまうなど、大田が納得できるようなものではなかった。
「無慾顔貌」を復活させ、出版の経緯を記した「序」も加えるなどした“復元完本”は1950年5月、冬芽書房から刊行される。しかしこれさえも、生原稿通りではなかったことが後に明らかになっている。
大田は1903年、現在の広島県北広島町に生まれた。1929年に「聖母のゐる黄昏」が雑誌「女人芸術」に載り、文壇デビュー。小説はなかなか評価を得られないでいたが、日中戦争が始まって以降は“国策小説”も書くようになり、流行作家になっていく。
1945年1月、空襲を避けるために東京から広島市に疎開。1945年8月6日朝、爆心地から約1・5キロの広島市白島九軒町の妹宅で被爆した。「緑青色の海の底みたいな光線」を受けたと、プレスコードが敷かれる前、8月30日付の朝日新聞に掲載されたエッセーに記している。
■西の家でも東の家でも
「屍の街」は倒叙法で書かれている。こんなふうに始まる。
「渾沌と悪夢にとじこめられているような日々が、明けては暮れる。よく晴れて澄みとおった秋の真昼にさえ、深い黄昏の底にでも沈んでいるような、混迷のもの憂さから、のがれることはできない。同じ身のうえの人々が、毎日まわりで死ぬのだ。西の家でも東の家でも、葬式の準備をしている。(中略)死は私にもいつくるか知れない。私は一日に幾度でも髪をひっぱって見、抜毛の数をかぞえる。いつふいにあらわれるかも知れぬ斑点に脅えて、何十度となく、眼をすがめて手足の皮膚をしらべたりする」
冒頭部分の時は1945年秋、場所は広島県廿日市市玖島(くじま)で、「私」は原爆から逃れてきている。そこで、原爆症に脅えて暮らしているのだ。
やがて話は時間を遡り原爆投下時に、場所も広島市内の爆心地2キロ圏内に移る。
被爆直後のくだりは、当事者の作家にしか書けない迫真性に満ちている。読者は「私」とともに、地獄絵図のような場所をさまよい歩くことになる。私は「屍の街」を読み終えた日の夜、悪夢にうなされた。
■人間の眼と作家の眼で
被爆2日目、「私」が土手から見た街は「瓦礫の原」で、死体は累々としていた。「眼も口も腫れつぶれ、四肢もむくむだけむくんで、醜い大きなゴム人形のようであった。私は涙をふり落しながら、その人々の形を心に書きとめた」
そう記した後で、大田は「私」とその妹のこんな会話をつづる。
「人間の眼と作家の眼とふたつの眼で見ているの」「書けますか、こんなこと」「いつかは書かなくてはならないね。これを見た作家の責任だもの」
第2次世界大戦時、日本の各地で空襲があった。大勢の人たちが逃げまどい、家を焼かれ、大切な人を亡くした。それぞれの苦しみや悲しみを比較することなどできないが、原爆の大きな特徴は、生き残った被爆者の多くが、病苦や強い不安に長く苦しみ続けたことにある。大田も死の影に脅え続けた。「屍の街」は被爆直後の悲惨さだけでなく、その後も続く恐怖と苦悩を早くも刻み込んでいる。
■被爆者置き去りにした復興を批判
「夕凪の街と人と」は、副題に「一九五三年の実態」とあるように、大田を思わせる作家の篤子が、被爆から8年たった広島を歩く。人々は心身の傷が癒えないまま、貧しさのなかであえいでいる。篤子は被爆当事者を置き去りにした復興の在り方を痛烈に批判する―。この作品の最初の出版は1955年だ。
このたびの岩波文庫が出版される少し前、小鳥遊(たかなし)書房から大田洋子原爆作品集2冊が出版されていることにも触れておきたい。
「屍の街 他11編」が2020年、「人間襤褸/夕凪の街と人と」が2021年に出され、それぞれ新版も出ている。両書の編者は日本文学研究者の長谷川啓(1941年~)。長谷川は後者の解説で「不安神経症に陥るまで原爆や冷戦に苦悩し、書くことで闘い続けた大田洋子の原爆文学の今日的意義は大きい。その問いかけはまさしく現代の問題そのものだからである」と述べる。
確かに、核の脅威は去らないばかりか、増大を続け、いつ臨界点を超えてもおかしくない状況に至っている。その脅威をさらに高めているのは、核兵器のもたらす徹底的な破壊と死、絶望について、私を含めた多くの人々が、具体的な知識や想像力を欠いていることだと思う。
そのような現在にあって、大田の原爆小説はまさに世界文学として、広く読み継がれなければならないと思う。大田が投げかける深くて重い問いを受け止めたい。(敬称略/田村文・共同通信編集委員)