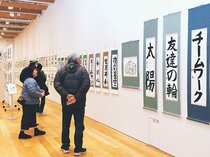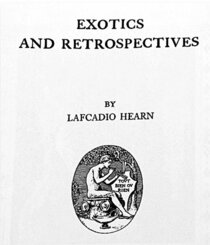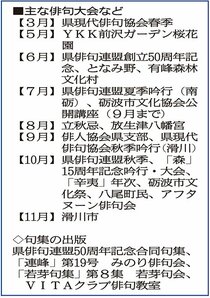今回は国内外から880編が寄せられた。応募数は前年から減ったものの、幅広い世代から力のこもった作品が集まった。特にシニア世代の挑戦が目立ち、数年前までほとんどいなかった90代以上の応募者が7人まで増えたほか、103歳の女性からの応募もあった。
応募作の題材は、年を重ねた主人公が人生を振り返り、感謝や後悔を語る―といった内容が多かった。子どもの発達障害やマッチングアプリを使った恋愛、物流業界などで叫ばれる「2024年問題」のような今日的なテーマに鋭く切り込んだ意欲作もあり、書き手の層は年々厚くなっている。
地元選考では7人の委員が最終候補作6編を決めた。昨年同様に抜きん出た作品はなく、委員の評価が分かれる場面もあった。
入賞作には、派遣社員として働く40代女性の暮らしぶりを淡々とつづった「月と鱧」が選ばれた。仕事に関する説明的な描写を最低限にとどめ、ワンルームマンションで1人暮らしをする主人公の生活や心情を軽やかな筆致で描いている点が目を引いた。
選奨の「子供を売る男」は幕末を舞台とした人情物語。北日本文学賞において、こうした時代小説が選奨までに入った例は多くない。作品世界にリアリティーを持たせる描写力や、無駄のない構成が評価された。
同じく選奨の「ちび丸の背中」は、親から虐待を受けた経験を持つ高校生を主人公に据えた。ともすれば重く暗い印象を抱かせる題材だが、SFのような雰囲気をまとわせ、読み手を物語の世界へ引き込むアイデアの秀逸さが支持を集めた。
最終候補に残った「師匠」は、学習障害のある少年が、家庭教師の大学生との交流を通して成長していくストーリー。難しいテーマに挑んだ27歳の若い書き手をたたえる声が上がった一方、2人に強いつながりが生まれた経緯などについて、もう一歩踏み込んであればと惜しむ意見も聞かれた。
最終候補入りを逃した作品からも、現代的なトピックを取り上げる挑戦意欲が感じられた。
佐藤文平(東京)「メール将棋名人戦」では、妻の認知症や老老介護と向き合う男性同士が、近況を報告するメールの中で一手ずつ将棋を指していく。ユニークな発想が光ったものの、題の付け方や結末に注文が付いた。高度生殖医療の現場を描いた浜田美鈴(兵庫)「パキラが枯れてしまう前に」は題材の目新しさに注目が集まったが、登場人物の挙動に対する違和感や不自然さを指摘する声もあった。鏡野響(福岡)「唯一の美しい夏」、寿美谷郡司(大阪)「大晦日」など、20代の書き手による作品も4次選考に残り、若手の台頭が感じられた。
県内からは浅野哲平(富山市)「落合のカメラ」が唯一、4次選考を通過した。「物語に破綻がない」と支持する委員もいたが、主人公が愛用のカメラに語りかけるシーンには疑問が残った。=敬称略(生活文化部・鴨島舞)