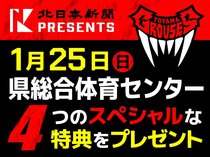私が1番子供に身につけさせたかった能力
いきなりですが、うちの息子の名前は、「大輔」と言います。
主人が付けたのですが、私も「だいちゃん」と皆から親しみを持って呼んでもらい、たくさんの友達と楽しい人生を生きていってほしいとの願いを名前に込めました。
でも名前や、親の思いだけでそういう子に育つわけではありません。毎日の生活の中で、家族とあいさつをし、食事や遊びを通して、人の気持ちや周りの空気を読む力を育てることが、コミュニケーション能力や社会性を育むことにつながると言えます。
そのためには、家族が触れ合え、愛情を確かめ合える環境が必要になります。
そもそもコミュニケーションとは?
「言葉や文字などで、お互いの考えや、気持ちを伝えあうこと」(旺文社国語新辞典より)
「コミュニケーション」を辞書で引くとこんなふうに書いてあります。
情報や気持ちを伝えるだけでなく、意思の疎通、心の通い合いという意味でも使われ、例えば、「親子のコミュニケーションをとる」は、親が一方的に話すのではなく、親子が互いに理解し合うことが大切になってきます。
コミュニケーション力が育まれる場所 我が家の場合①
ひとつ目は、家族が触れ合えるキッチンです。家づくりも、ひと昔前は、家族が集まる場所=リビングでしたが、最近は共働きの夫婦が増え、家で家族が過ごす時間が少なくなったことから、ダイニングキッチンを家族が集う場所として設計されることが多くなってきました。
また、「火のある所に人は集まる」「食のあるところに人が集まる」と言います。
そんな人が集まりやすい場所、そして生きていくために本能的に求める場所は、コミュニケーション能力を育てるにはもってこいです。
私の経験でも、コミュニケーションが少なくなる思春期に、役立ってくれたのがキッチンでした。
息子が高校1年生のとき、閉鎖的なキッチンからオープンキッチンにリフォームしました。息子は朝ごはんをキッチンで食べるようになり、お弁当を仕込んでいる私とのコミュニケーションの時間ができ、学校のことを話してくれるようになりました。
面と向かって話すことは抵抗がある思春期の息子も、作業をしながらだと話しやすいですし、片付けやすいので「ありがとう」を伝えることもでき、朝から心が通い合った実感がありました。
コミュニケーション力が育まれる場所 我が家の場合②
二つ目はお風呂です。我が家では、中学生まで息子と父親が一緒にお風呂に入っていました。
リラックスできるお風呂タイムは、心身ともに密接な関わりができ、お互いの言葉がより心に深く届くように感じていました。
息子は、サッカーのクラブチームに所属していたので、会話はその報告や悩みが中心だったようですが、聞いてもらって気持ちが落ち着いた。気持ちがスッキリした。と、いう経験ができれば、周りの人が悩んでいた時、同じように話しを聞いてあげることできると思います。
コミュニケーション力が育まれる場所 我が家の場合③
最後、3つ目は、やはり家族が集うリビングです。
行儀が悪いと感じられる方もいるかもしれませんが、我が家では食事の時間にテレビがついています。
育児への影響を考えたとき、テレビはあまり見せたくないと思われる親御さんもいらっしぃますが、我が家ではそのニュースについてどう考えたか、感じたかを話し、学校で友達とも話していたようなので、会話を生むコミュニケーションツールになっていました。
何もしなければ、テレビは受け身のメディア。それを能動的に変えていくことで、子どもにとってはもちろん、親にとっても子供の考えを知るよい時間になりました。
子どものうちは、コミュニケーションも、社会性も、家族から学びます。
コミュニケーション力を高めるには、私たち親の役割が大きいのです。
次回は最後になります。「生きる力のある子を育てる空間」です。

◆浮田 美紀子(うきた・みきこ)◆
整理収納アドバイザー、骨格スタイルアドバイザー、家事代行会社経営。
富山市出身。住宅関連企業を経て2012年に整理収納アドバイザーとして活動を開始。県内の主婦グループ「シュフーレ」を立ち上げ、暮らしに関連する講座を担当する。2016年に家事代行や整理収納のほか終活サポート、宅食サービスなどを行う会社を設立。大学生の長男がいる。