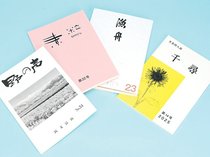真言宗薬勝寺(富山県射水市日宮)にあり、2024年元日の能登半島地震で損壊した虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)像が、室町時代に作られたと推定されている小矢部市指定文化財の「木造虚空蔵菩薩坐像」と酷似し、同じ仏師が作った可能性があることが分かった。修復の過程で明らかとなった。修復された仏像は新調した厨子(ずし)に納められ、27日に同寺で行われた大般若で、関係者が復活を祝った。
薬勝寺には、市指定文化財の「木造釈迦(しゃか)如来立像」「木造十一面千手観世音菩薩立像」があるが、御堂の中央に安置されている虚空蔵菩薩像は文化財に指定されておらず、由来や歴史的価値も不明だった。能登半島地震直前の23年12月、日本石仏協会理事の尾田武雄さん=砺波市=らが虚空蔵菩薩像を調査。「宝剣」と「宝珠」を手にしていることから、由緒ある仏像である可能性が判明した。
虚空蔵菩薩像は木製で台座も含めて高さ約80センチ、幅約30センチ。地震で燭台(しょくだい)が倒れて直撃し、台座や光背が砕けた。薬勝寺は先祖が同寺を建立した射水市橋下条出身の星野尚美さん=東京都練馬区=を介し、金沢市の仏師に修復を依頼した。その後、小矢部市指定文化財の「木造虚空蔵菩薩坐像」と酷似していることが判明。薬勝寺の虚空蔵菩薩像も同時期に同じ仏師が作った可能性があると分かった。像の内部から観音像が見つかったことも関係者を驚かせた。
27日は尾田さんや星野さんら約50人が参列し、中川清明住職らが像の前で読経した。中川住職は「目に留まる機会が少なかった虚空蔵菩薩像が地震を機に注目が集まるようになり、匠(たくみ)の力で修復できた。言い伝えとともに大切に守り伝えていきたい」と話した。