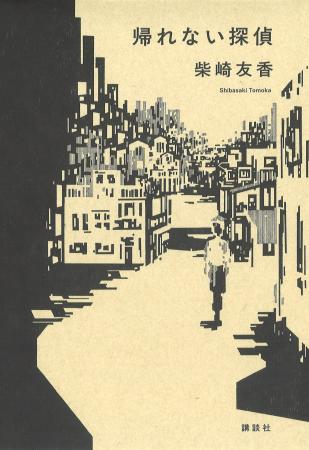人間には限られた年月しか与えられていない。仕事でも恋愛でも人生でも、いつかは終わりが来る。私たちは「永遠」「永久」「無限」という言葉を使いこなしているつもりだが、本当かどうかを確かめられる人はいない。ただ、有限を乗り越える想像は自由だ。その意志を運ぶのが文字、そして物語だろう。
柴崎友香の新刊「帰れない探偵」の主人公「わたし」は、生まれ育った国を十年前に離れ、さまざまな国で調査の依頼を受けている。探偵が語り手となる連作だが、派手な事件は起こらず、各編の冒頭と最後にこんなフレーズが繰り返される。「今から十年くらいあとの話」「これは、今から十年くらいあとの話」。
近未来を感じさせるその世界では、巨大企業が情報を管理し、個人のプライバシーも把握されているらしい。歴史や地図も都合よく書き換えられていることがうかがえる。「わたし」の国も体制が変わってしまった。
柴崎は具体的な国名を記さず、「わたし」にはコードネームとしての番号しかない。名前を持つ登場人物でさえ一人一人「(仮名)」と文中で断りを入れている。この作品では時間も空間も個人も確実なものではない。
舞い込む依頼は四十年前に起こった事件の関係者からの聞き取りや、移民の子孫のルーツ調査など記憶に関係している。しかし私たちは歳月にさらされた記憶が修正され、創造されることを知っている。記憶は確実でも不変でもない。
絶対ではないそれらの記憶を集め、帰る所をなくした探偵とは、私自身ではないか。ページを繰りながら落ち着かない気分になる。たくらみを感じる連作だ。時間は誰にでも同じ長さで、決して後戻りしないと思い込んでいる頭を揺さぶられた。
人間の時間には限りがあるが、思考と意志を記録する文字は個々の人間よりも長く命を保ち、後世の人間に影響を及ぼしている。書物を手で写していた中世ヨーロッパで活版印刷技術がグーテンベルクによって確立され、黒いインキの整った活字で複製された文字は、その時間を飛躍的に延ばし、世界に広がった。
印刷博物館(東京都文京区)の「黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化」展(7月21日まで)は、15世紀半ばのドイツで「黒い魔術」という意味の名称があった活版印刷が、当時の文化、思想の変化を促した歴史をたどっている。
グーテンベルクによる「42行聖書」、宗教改革に関するルターの文書や全集など、黒々とした活字が占めるページの迫力に引きつけられた。グーテンベルクが聖書の印刷に用いたブラックレター(ゴシック体)はドイツ文化を象徴する文字になり、長く20世紀まで常用されたという。それらを収めた本展図録にも見入った。
この春、印刷博物館館長に就いた作家の京極夏彦は図録に「わたしたちの暮らす現代社会は、グーテンベルクの“黒い”版面の上に築かれたといってもいいでしょう」と記している。人間の意志を文字に乗せ、時空を超えて運ぶのが複製の技術であると再認識した。それを「黒い芸術」と本展は捉えている。
「帰れない探偵」では、音楽が時空を超える大切な役割を担っている。「わたし」は思う。「どこに行っても音楽がある。どこの街へたどり着いても、音楽があればそこに居場所がある気がする」
音楽はペーパーウエイトのように「わたし」を過去から逃さないが、悪いものではない。ビートルズの「Tomorrow Never Knows」や、ザ・ブルーハーツの「終わらない歌」から呼び起こされる記憶は「わたし」にとって懐かしく、勇気を奮い起こす。
限りある時間を超えるために、人間は芸術を求めるのだと思う。(杉本新・共同通信文化部記者)
【今回のリスト】
▽柴崎友香「帰れない探偵」
▽印刷博物館「黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化」展