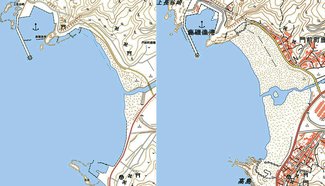能登半島地震による液状化被害が甚大だった富山県氷見市栄町の新道地区で、復興に向けたシンボルとして花畑の整備に取り組む住民が6日、被災家屋が公費解体された更地にコスモスの種をまいた。氷見高校生や被災後に地区から転出した人も参加。「花が満開になる10月にまた集まろう」と誓い、作業に汗を流した。
新道地区の世帯数は地震前は約80だったが、50ほどに減った。海に近く、特に被害が大きかった県道薮田下田子線沿いはほとんどが地区を離れ、今は3世帯が残るだけという。
以前は約15軒が並んでいた県道沿いの更地約1100平方メートルのうち約500平方メートルに種をまいた。市の地域コミュニティー維持支援事業の一環で、氷見高校農業科学科の生徒たちが5月下旬から植える花を決めたり、更地を耕したりして準備に協力してきた。
この日は転出した人を含め住民35人、氷見高生7人が参加。新道町内会の山崎勇人会長(62)は「多くの人が集まってくれたことに感謝」と笑顔を見せた。今のところ更地に自宅を建て直す人はいないというが、「みんな地区への思いは持っている。離れた人が戻ってこようと思ったり、地区とつながり続けたいと感じたりするきっかけになればいい」と力を込めた。
種のまき方を指導した氷見高3年の谷内妃希(やち・ひなの)さん(17)は「復興に向けたお手伝いができていることがうれしい」と話し、新道地区震災復興期成会の鎌和紀会長(73)は「復興まで時間はかかるだろうが、花の世話を続けることで、きっとまた住民たちに地区への愛着が湧いてくるはず」と語った。
近くに住む浜元維子(ゆいこ)さん(32)、侑ちゃん(4)の親子は種をまきながら「家が減って寂しくなった新道にまた人が集まってきてほしい」と願った。