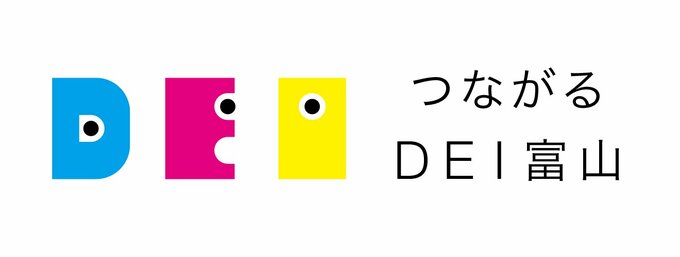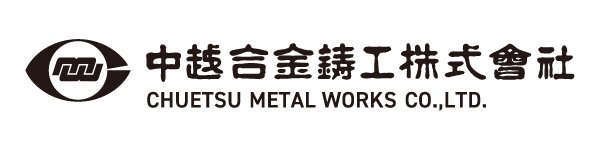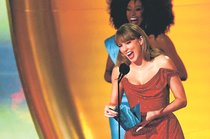6月23日から29日は、男女共同参画週間。1999年6月23日、男女共同参画社会基本法が公布・施行されたことを踏まえ設けられました。それから26年、社会はどう変わったのでしょうか。海外の事情にも詳しい富山大学国際交流サークルの学生4人に、今の日本社会をどう感じているのか聞きました。(協力:富山大学ダイバーシティ推進センター)

魚住康太さん(人間発達科学部4年、富山県出身)
根岸知世さん(医学部2年、茨城県出身)
米田美和さん(経済学部4年、富山県出身)
ルゥンデブ・テムーレンさん(経済学部3年、モンゴル出身、本文中はテム)
 「女の子なんだからお手伝い」に違和感
「女の子なんだからお手伝い」に違和感
――子どものころから現在までを振り返って、男だから、女だからと言われたり、性別や国籍などの属性を理由に制限を受けたりしたことはありますか?
根岸:行動を制限されることまではないですが、親せきが集まったりする時、母親たちは料理を作ったり運んだりしますよね。そんな時、「女の子なんだからちゃんとやらなきゃ」と言われたことがあって「男の子だったらやらなくていいの?」と思った記憶があります。
米田:親世代には「若い女性=きれい。だから結婚は若いうちにしたほうがいい」という意識があるのを感じます。内心、ふざけんなと思ってますけど。女性って別にきれいだけが価値じゃない。芸術作品じゃないんだから。その人の仕事ぶりとか、性格とかも大事。そもそも年齢関係なく、女性はいつまでもきれいでいられると私は思っています。
テム:女性へのステレオタイプな考え方はモンゴルも同じです。ただ一つ違うのは、モンゴルの家庭では、女性のほうが経済的にも精神的にも男性よりパワフル。私のママもパパの3倍稼いでいるし、何か相談するならまずママに話しますね。
魚住:昨年、フランスで7カ月、有償ボランティアの活動をしていたのですが、経験的に「この地域の人、この宗教の人は、こういう考え方なんだろうな」と無意識に働いてしまいます。それがあるから、配慮もできて人間関係がうまくいくこともあれば、もうちょっと深い関係を築こうとすると、その思い込みが壁になることもありました。
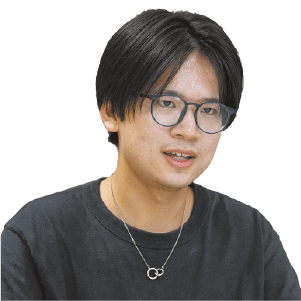 学校の掃除は子どもがやるのに、家ではママ任せ、なぜ?
学校の掃除は子どもがやるのに、家ではママ任せ、なぜ?
――違う国の人たちと話すことで、日本社会の特徴に気付くこともあるのではないでしょうか。
テム:日本人の男の同級生から、部活で使う服や弁当を全部ママに準備してもらっていたという話を聞いて驚きました。海外のメディアで日本では小学生の時から自分たちで教室を掃除するという話題がよく取り上げられますが、家庭だと全部ママがやるのはなんで?モンゴルでは学校の掃除は専門の人がやるけど、家庭では子どもたちが結構やるので、ママにそんなに負担はかかりません。
根岸:私は高校時代、1年間イギリスに留学していました。ホストファミリーは子どもが4人いる家庭で、子どもたちは小学校2年生くらいから、簡単なサンドイッチのようなお弁当を自分で作っていました。そういうことが、子どもの自立を促していたのかも。
米田:親に頼ってきたのは私も同じ。子どものころから両親や祖父母たちの、男女の役割分担を見てきて、家事は親がやるものという先入観があるんだと思います。
魚住:親自身の責任感もすごく強い。特にお母さんの責任感、えげつないですよ。「結局、自分がしなきゃダメなんでしょ」みないな感じです。一方の父親も、家族のために稼がないといけないという使命感があって、子どもは学問が仕事という風になっている。
根岸:母親のその責任感、次の世代の自分たちが背負うのはつらい。私の場合、家事は任せっきりにはしてなくて、お弁当も自分で作っていました。母には母の人生を歩んでほしいから。
 就活で重視したのは年功序列ではない会社
就活で重視したのは年功序列ではない会社
―これから働くことになる皆さん、就職する際に重視することは?
米田:若い社員でも意見が言えて、やりたい仕事に取り組める、年功序列ではないという点を重視しました。ここからは私の偏見ですが、富山は県民性として、割と上下関係がしっかりしていて、ルールからはみ出ることは良くないみたいな考えが強い。だからこそ社会が安定しているとも言えるけど。私は自分の意見はしっかり主張したいほうなので、首都圏で就職活動をしました。
テム:私もダイバーシティ(多様性)を重視しています。日本の企業や大学のホームページを見ていると、同じようなおじさんが多いですよね。そういう所は嫌だなと思っていて、いろんな人がいる集合体みたいな会社を探しています。
根岸:私はマルチナショナル(多国籍)なところに行きたい。
魚住:しばらくはいろんな国へ行って、人生の冒険をするつもり。自分が少数派になる場所にいると、新しい考え方を取り入れ、臨機応変に行動できるようになる。ただ冒険ができるのは、いつでも戻ってこられる環境があるからなんです。海外に出て思ったのは、階級意識や人種への偏見がまだ残っているヨーロッパに比べれば、日本の労働環境は全然悪くない。さらに富山は自然が豊かで、治安も良くて、すごく暮らしやすい。
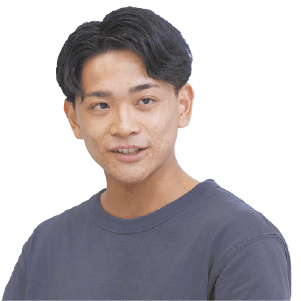 若いうちは冒険したい 戻れる場所があるから
若いうちは冒険したい 戻れる場所があるから
――富山県は若い女性の転出が多く、県では対策を検討しています。
テム:良い言葉を知っています。チョウは追いかけたら逃げちゃうけど、きれいな花を育てておけば、自然と集まってくる。これ、富山県でできるんじゃないかと。
米田:富山は製造業が多くて、逆に言うとそれ以外に選べる仕事が少なかった。「きれいな花」の一つとして、仕事の種類が増えれば、県内で働こうという人も増えるのかも。それに若い人が県外に出て行くというのは、そこまでネガティブな話じゃない。成長を求めて外へ出る人ということはポジティブなことでもあるから。
――皆さんが思う、自分らしく輝ける社会とは?
テム:時代に適応して、変化できる社会であれば、自分らしく輝けるんじゃないかな。
魚住:変化に対応するということは、まず自分がどんな人も受け入れるということ。誰かにマイノリティーであることを伝えられても「うんうん、そうなんだ」ぐらいの心持ちで答えれば、相手もうれしいだろうし、そこに快適さが生まれると思う。
米田:私は、変化を受け入れ、かつ変化が頻繁に生まれるような環境を、いつか富山に作りたいと思っています。そのために今の自分にできることは、意見が他の人と違っていいと主張すること、みんなと違うからって黙らないことかな。
根岸:私ができることは、自分より若い世代に、私が見てきたことや世界のことを伝え、「自分と違う人がいてあたりまえだよ」と教えてあげること。意識を変えられるようなことができたらなと思っています。

今年のキャッチフレーズは「誰でも、どこでも、自分らしく」。男性も女性も、職場や地域、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる社会を実現するため、県内でも講演やワークショップ、パネル展示などが行われます。
わたしたちは、互いに認め合いながら
自分らしく輝ける社会を応援しています
(五十音順)

DEI(ディー・イー・アイ)は、多様性(ダイバーシティ)、公平性(エクイティ)、包括性(インクルージョン)を意味する言葉です。性別、年齢、国籍、出身、性的指向、障害の有無…人と人との間に横たわるさまざまな違い。DEIは、これらを互いに認め合い、それぞれの能力を最大限に発揮できる環境づくりを進める考え方です。北日本新聞社広告キャンペーン「みんなでつなぐDEI」では、誰もが自分らしく輝ける社会について考えます。
企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局