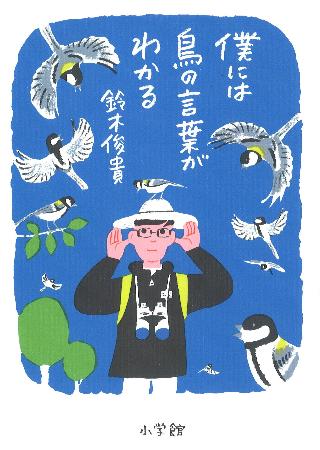「僕には鳥の言葉がわかる」(鈴木俊貴著)を読みながら、何度も「面白いなあ」と声が出た。シジュウカラの特定の鳴き方に意味を見出し、2語で文を作っていることも明らかにする。著者は大学の学部生の時からこの声に着目し、実験を積み重ねて国際的な学会や科学誌で認められていく。そして動物言語学という新しい学問を切り拓いた。そのステップが明朗な文章でつづられている。
著者の主張はこれまでにもテレビ番組などで目にしていたが、本書で改めて驚いた。「人間だけが言葉を持つ特別な存在ではない」「人間には人間の言葉があるように、シジュウカラにはシジュウカラの言葉がある」。専門家のこれまでの常識、つまり「言葉を操ることができるのは人間だけで、動物の鳴き声や仕草は単なる感情の表れに過ぎない」という考え方を著者は科学の手順で覆していく。
軽井沢の森にこもり、自作の巣箱でシジュウカラを集め、録音した鳴き声を編集して聞かせ、行動を観察する。実験でシジュウカラに危機感を抱かせるためアオダイショウや動物の剥製を携えて機材と共に毎日十数キロ歩く。他の研究者から反論を想定してさまざまな可能性を一つずつ検証する。
「動物は言葉を持たない」という固定観念を打ち破るには地道な作業を繰り返すしかないことがよく分かる。仮説の証明に注ぐ高い熱量と科学者の厳密な仕事の一端を教えられた。
シジュウカラは自分たちを狙うアオダイショウやモズが現れると、「ピーツピ、ヂヂヂヂ」と鳴く。これは「ピーツピ」(警戒しろ)、「ヂヂヂヂ」(集まれ)を意味する2語の文で、実際に敵に対してその通り行動する。編集で語順を逆にした「ヂヂヂヂ、ピーツピ」という声を聞かせても動かない。
まだ外の世界を知らないヒナは、外敵に応じて親鳥が発する声を聞き分け、ある声の時は巣の中で身をかがめ、ある声では外に初めて飛び出す。異なる声の意味を的確に理解しているのだ。
常識を覆し、世界を変える独創性を生むのは、理想を諦めない明るさだと感じる。実は私たちの日常にも必要なのかもしれない。親しみやすい筆致に引きつけられて科学者を志す子どももいるだろうが、ぜひ大人におすすめしたい。今年1月の刊行から部数を伸ばしている本書はこの6月、今年の河合隼雄学芸賞に決まった。
鳥の声に感動したので、鳥にまつわる曲をいくつか取り出して聴いた。まずはビートルズ、というよりポール・マッカートニーの「ブラックバード」。グラミー賞のビヨンセのアルバムでもカバーされていたが、黒人解放運動に共鳴した作品が心にしみ通る。ちょっと前のことになるが、2013年の東京ドーム。ポールが生ギターだけでこの曲を歌い、ドーム全体が静かに聴き入った。私もその場で心を震わせた1人である。
バードと言えばもちろんチャーリー・パーカー。飛翔するようなアルトサックスの演奏からそう呼ばれたとも言われる。ここでは、鳥の絵が描かれたジャケットもある「ウィズ・ストリングス」を。弦楽をバックに、はばたきにも似たアドリブのリズムと連なりが、楽しく気分よく聴こえる。
最後にニーナ・シモンの「I wish I knew how it would feel to be free」を選ぼう。パワフルかつ繊細な表現が魅力の彼女の歌声にはいつも励まされる。公民権運動を背景にビリー・テイラーが作ったこの曲でも、自由であるとはどんな感じなのか知りたいと願う歌詞に次の一節がある。…like a bird in the sky…そう、空飛ぶ鳥のような自由もまた、世界を変えると信じたい。(杉本新・共同通信文化部記者)
【今回の作品リスト】
▽鈴木俊貴「僕には鳥の言葉がわかる」
▽ポール・マッカートニー「ブラックバード」
▽チャーリー・パーカー「ウィズストリングス」
▽ニーナ・シモン「I wish I knew how it would feel to be free」