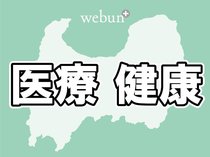富山大の研究チームは、高難度の膵臓(すいぞう)手術「膵頭(すいとう)十二指腸切除術」の術後経過不良と関連がある二つの危険因子を世界で初めて突き止めた。胃や大腸の手術と比べて高いとされる死亡率や合併症のリスクを予測し、手術を行うかどうかの判断基準とすることで、より安全な治療につなげる。
膵頭十二指腸切除術は膵臓がんや胆管がんなどに行う手術。膵臓の近くには血管や神経が集中しており、手術には高度な技術が求められる。死亡率が約3%、術後に重篤な合併症が起こる割合が30~40%とリスクが高い一方、これまでは手術の可否を判断する明確な基準がなかったという。
研究では同大で膵頭十二指腸切除術を行った65歳以上の311人を対象に調査を実施。国内の症例を登録したデータベース「National Clinical Database(NCD)」で、予測される術後のADL(日常生活動作)低下の発生率と、重度合併症の発生率の2項目が一定の数値を超えると、術後経過不良発生率が100%となることが分かった。
NCDに患者の情報を入力し、予測される術後経過不良の発生率が高い場合、栄養管理やリハビリなどの対策でリスクを下げて、より安全に手術することが可能となる。同大付属病院ではこの基準を活用しており、過去4年間の手術約270例での死亡はゼロだったという。
9日、杉谷キャンパスで記者会見があり、同大付属病院消化器外科の藤井努教授(56)は「患者にとってより良い結果を手術前に調べることができる画期的な方法」、木村七菜病院助教(32)は「他の手術に生かし、死亡率や合併症のリスクを下げていきたい」と話した。
研究は5月、国際学術誌に掲載された。