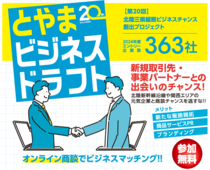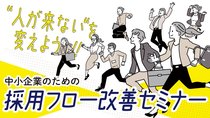県内企業4社の若き後継者(アトツギ)たちが集結。創業より培われてきた経営資源をどう受け継ぎ、今後の事業・組織の前進にどうつなげていくかについて、また、来年1月に地方予選大会の開催が迫る中小企業庁主催「アトツギ甲子園」について熱く語りあった。
登壇者

大征工業株式会社
取締役専務
棚元 将太郎 氏(29歳)
1970年、祖父が創業し、89歳の今も現役で代表取締役を務める大征工業の2代目。現在は、ステンレスねじ、プレス金物、ドア・サッシの機構部品など、各種製品の生産管理・生産技術開発に携わる。目標は、楽しく仕事に打ちこめる環境を整えることと、富山県を代表する会社をつくること。 Instagramでは3.1万人のフォロワーをもつ。

宮越工芸株式会社
主任
宮越 若菜 氏(27歳)
1950年、曾祖父が高岡銅器着色の工場として創業し、現在はアルミ建材などの塗装を行う宮越工芸で、事業承継に備えて入社以降、各部署の業務を経験。現在は主任として営業活動に従事しており、習得すべきことの多さにとまどいつつも、明るく前向きに奮闘中。塗装への理解を日々深め、魅力的な提案につなげている。
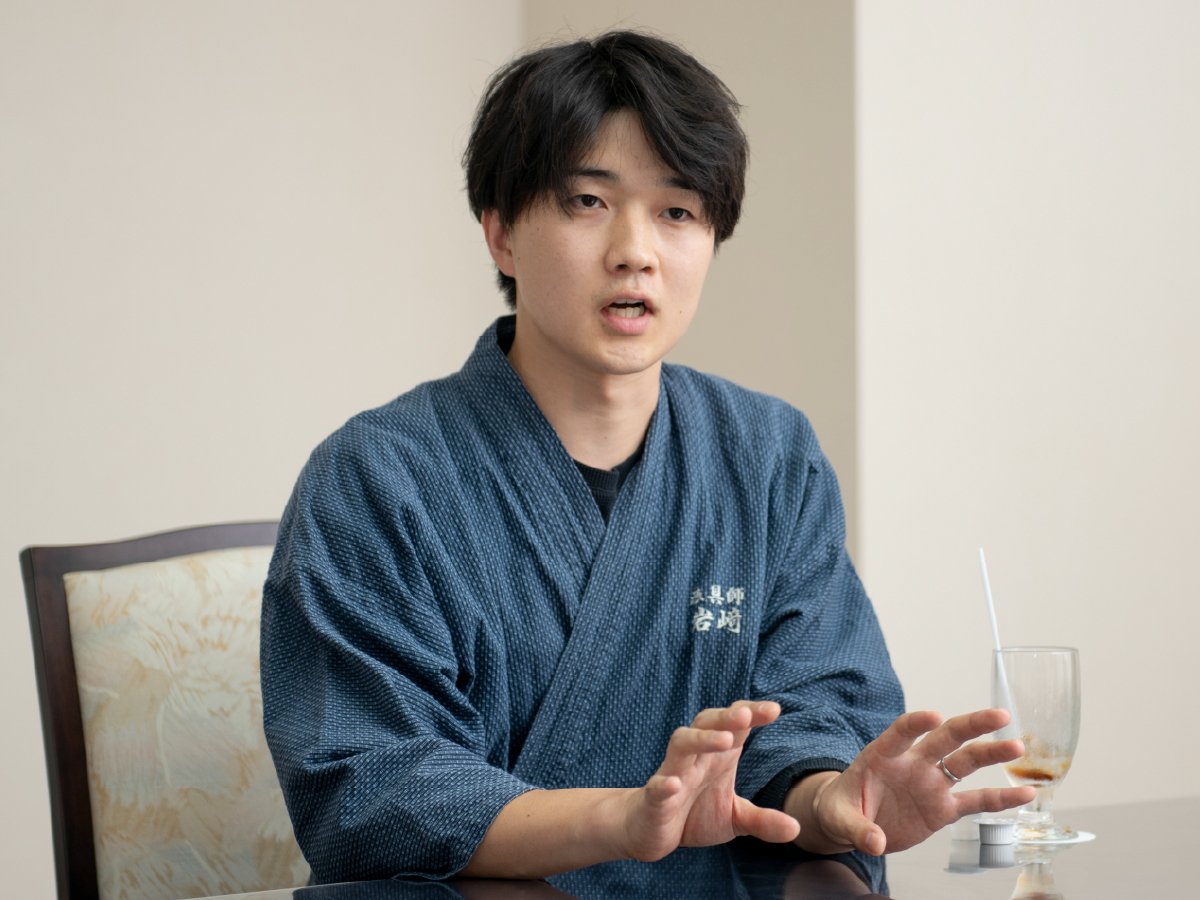
岩﨑精正堂
岩﨑 太成 氏(29歳)
祖父・父と続く岩﨑精正堂の3代目。19歳のとき米国に渡り、ボストン美術館などで活躍した日本画修復師 西尾喜行氏に弟子入り、約3年間、修復を学ぶ。帰国後は習得した知識・技術を活かし、掛軸、屏風、額など表具全般を修繕。台湾の大学院で教鞭をとるなど、知識・技術の継承や後進の育成にも努める。

アルミファクトリー株式会社
代表取締役社長
棚元 優太 氏(27歳)
今年1月、父から事業承継を受け、アルミファクトリーの代表取締役社長に就任。第4回「アトツギ甲子園」では、「日本の避難所に「いごこち」を届ける」で準ファイナリストに選出。通常時はパーテーションに、非常時はベッドになって雑魚寝をなくす防災用品「IG-A」が高く評価された。
後継者が承継し、挑戦したいこと

承継したいことは祖父で創業者の棚元 弘が大切にする"らせん思考"です。過去の経験や成果を踏まえて品質や効率を上げていこうとする考え方で、当社では「昨日の創意工夫はもう古い」という合言葉のもと、社員一丸となって改善を追求しています。加えて、スピーディーな対応によるお客様への奉仕も大切にしており、このような日々の積み重ねが、現在の業績向上や企業発展をもたらしていると実感しています。挑戦したいことは後継者不足に悩む会社の支援です。SNSで3万人超のフォロワーを獲得するなど、これまでに培ってきた経験を活かし、メディア戦略を含めたマーケティングなど、業務単位でのお手伝いができればと考えています。それぞれの会社の強みを見つけて、ぐんぐん伸ばしていきたいですね。

先代が承継したいもののひとつに社是があります。「会社の信用を重んじ、顧客に満足される製品を供することによって、広く社会に貢献する。」「英知を育て創意工夫をはかり、常に経営の前進に努める。」「和と協調につとめ会社の総力を結集する。」という内容なのですが、じつはいま私にその再解釈が求められているんです。現状との擦りあわせが必要になることもあり、どう再解釈しどう承継していくか、答えは明確になっていません。けれど、人あっての現場、現場あっての会社なので、そこは大切にしたいと思っています。一方、なにに挑戦したいかは明確になっています。中小企業で働くワクワクを体感できる機会の創出です。私自身、中小企業で働いていて毎日とても楽しく、ひとりでも多くの方に中小企業への就職を選択肢にくわえてもらいたいので、そのきっかけとして、アトツギのみなさんとクロストークをしたり、富山でのアクティビティを楽しんだり、一緒になにかできればと考えています。

海外で学んできた知識と経験を活かしながら、地元富山でひとつひとつ目の前の作品とお客様に真摯に向き合っていきたいです。同時に、大学院で教えたり、インターンを受けいれたり、知識・技術を承継することや後進を育成することも大切にしていきたいですね。また、和室離れが進む現代に合った掛軸「かけフォト」にも力を入れていきたいです。掛軸を少しでも身近なものに感じてもらえるきっかけになったらうれしいです。「かけフォト」は和紙に印刷した写真を表装した新しい掛軸。床の間以外の場所にも飾れるデザインにしたところ反響があり、製作依頼が増えてきています。今後、インテリアとしてのニーズが高まれば、担い手が求められるようになり、表具師人口の増加が期待できるのではないでしょうか。富山県は他にくらべて表具店が多い地域ではありますが、かつて100軒ほどあったのがいまは30軒ほどに減っているので、表具業界の活性化の一助にもなればと考えています。

現場にこだわる祖父とグループ全体を俯瞰する父、方向性が全く異なる両者の経営に触れるなかで、私が目指したいと考えたのは、社員が主体的に行動するボトムアップ型の組織です。その手始めとして、代表取締役社長に就任後、ふたつの改革を実施しました。ひとつは作業着の自由化、もうひとつは社内表彰制度の自薦応募化で、後者については、主体性を発揮した社員が高く評価されるという意識の浸透につながるのではないかと期待しています。メーカーとしての道を拓こうと続けてきた自社製品の開発も、目指す組織の実現によい影響をもたらしてくれるのではないでしょうか。「大切な人を守る為に成長する」という経営理念から、「大切な人を守るためのモノづくりをしては」という助言をもらい、たどりついた防災用品という回答。今後、開発や製造を進めるなかで、社員がどのような主体性を発揮し、組織がどのように前進していくのか、楽しみな気持ちがふくらんでいます。
「アトツギ甲子園」で得られるもの

「アトツギ甲子園」に参加できるのは中小企業・小規模事業者の後継予定者のみ。だから、参加できるだけでチャンスなんです。しかも、参加すればたくさんのメリットが得られます。私の場合、ひとつは、自社のありかたを振り返る機会。自身がプレゼンテーションをすること、他者のプレゼンテーションを見ることで、事業や組織を客観視でき、その価値を再確認できました。もうひとつは、全国各地のアトツギ仲間との関係構築。これはなによりのメリットといっていいのではないでしょうか。業種は違えど、ひとりひとりが熱くて前向き。交流するたびに、新規事業アイデアのヒントをもらい、「もっと頑張ろう!」とエネルギーが湧いてきて、よい刺激になっています。

アトツギの方々とお話しするようになって数カ月ですが、さまざまな集まりに参加し、皆さんと話をするなかで、たくさんの刺激をもらっています。視座が高くなり、背筋が伸びて、仕事にもいい影響がでてきていますね。交流の機会は今後もあると思うので、今からワクワクがとまりません。私と同じようなことを考えている方と、業種・地域問わず意気投合して、面白いことをはじめられれば最高ですね。

以前、将太郎くんに誘われたときは、正直あまり乗り気ではなかったのですが、今回、参加してみて本当によかったと感じています。自身を振り返る機会になっていますし、仕事量の減少に危機感を抱く私にとっては、現状打開をはかる機会にもなっているからです。今回のプレゼンテーションでは、客観的な評価を得て、課題や改善点を見つけたいですね。そして、「かけフォト」が現代の住空間になじみ、若年世代にも親しまれる表具となるよう、さらなるブラッシュアップをはかりたいと考えています。

参加してうれしかったのは、防災用品の開発という私の取り組みに、社員が理解を示し期待を寄せてくれたことです。最初は「つくったところで売れるのか」「製造の手がまわらない」と反発があったのですが、大会で発表したあたりから、「可能性があるかもしれない」と好意的な雰囲気に変わりはじめました。また、プレゼンテーションを見て入社してくれた方がいたり、他の防災用品メーカーからの依頼につながったり、人材獲得や事業拡大にもいい影響が表れてきました。兄が語った「全国各地にアトツギ仲間を得られた」というのも全くの同感。ただ仕事をしているだけでは出会えない、圧倒的な熱量をもつ方々とつながれて、本当にありがたいと思っています。
アトツギのみなさんへメッセージ

「アトツギ甲子園」はそうそうないチャンス。応募資格があるなら、参加しないという選択肢はないのではないでしょうか。そして、参加すると決めたら、「成果をつかみとってやる!」という気概をもって取り組んでほしいですね。それぐらいじゃないと、経営者としてやっていけないのではないかとも思っています。もうひとつ伝えたいのは、先代のみなさんからも参加をすすめてほしいということ。アトツギの育成はもちろん、自社の認知度向上や事業PRにもつながる、またとない機会になるはずです。

新規事業のアイデアは、人と出会って、聞いたり、話したりすることで生まれるもの。富山は都会にくらべると人と出会う機会が圧倒的に少ないので、こうした状況を打破するためにも参加してみるといいのではないでしょうか。私もみなさんに出会って、学びや気づきをもらうとともに与えられればと思っています。そして、それを活力に変えて、さまざまな世代・背景の人たちが集まり、ともにモノづくりをする会社という場所をもっと面白くしていきたいと思っています。

「アトツギ甲子園」で競うのは新規事業アイデア。この"新規"というところに難しさを感じ、着想に至れない、参加に踏みきれないという方は、いまある強みを伸ばしていく・広げていく方向で考えてみるとよいのではないでしょうか。実際、私も、ひと通りの業務を経験し俯瞰できるようになって、「かけフォト」というアイデアにいきつきました。時間はまだあるので決してあきらめず、ともに頑張りましょう。

私は、今年、代表取締役社長に就任し、後継予定者から後継者になりました。ですので、「アトツギ甲子園」には参加したくても参加できないんです。そういった方は他にもいらっしゃると思うので、参加できる方はこの機を逃さずぜひエントリーしてください。今後の職業人生で財産になるものがきっと見つけられます。