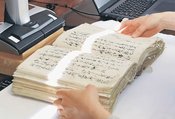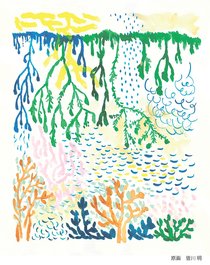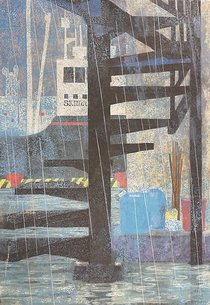富山県南砺市の城端別院善徳寺は5年前から、所蔵する古文書をデジタル化し、全国のくずし字愛好家らとオンラインで共有して解読を進めている。寺によると、全国でも例がない取り組みといい、専門家は「民間の手による史料解読のモデルケースになる」と指摘する。
真宗大谷派の善徳寺は江戸時代、本山や加賀藩と、管轄する寺院との間で下達や上申を仲介する「触頭(ふれがしら)」で、情報が集まる一大拠点だった。約9千点の古文書が残るが、多くは内容を解読できていなかった。
「地元で解読員を確保するのは難しいが、インターネットならできる」。寺の関係者から相談を受けた浦辻一成さん(69)はオンラインでの解読事業を発案。NPO法人「善徳文化護持研究振興会」(善文研)が設立されると、浦辻さんは古文書調査班長に就任した。
2020年から古文書をスキャンして画像にする作業を開始。解読者を全国に募り約40人を集めた。難易度別に割り当て、読み解いた結果をテキストデータで送ってもらい、上級者がチェックする。
浦辻さんによると、古文書は人々の暮らしぶりが分かるメモ類が多いという。幕末の京都で、鉄砲などが運び込まれる薩摩藩邸周辺の不穏な動きを伝える善徳寺宛ての書状もあった。
スキャンはおおむね完了し、解読も6割が終わった。24年から一部をネットで公開しており、27年までにほぼ全てを閲覧できるようにする予定。浦辻さんは「資金面で苦労はあるが、研究に活用されることを期待している」と語る。
善文研の客員研究員を務め、人文学資料のアーカイブ化に詳しい国立歴史民俗博物館の橋本雄太准教授は「これほど大規模な史料の解読が、民間で実現されたことに驚いた。古文書が残る各地の寺に、この取り組みが広がればいい」と話している。