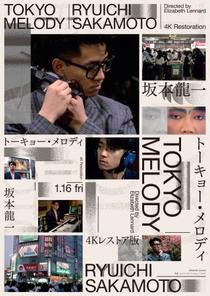長く勤めた新聞社を50歳で退社した元朝日新聞編集委員の稲垣えみ子は、40年ぶりにピアノの練習を再開した。時間はたっぷりある。意欲も、弾いてみたい曲もある。だが一向にうまくならない。「努力すれば弾けるようになるだろうと思って一生懸命頑張ったのに、どうにもうまく弾けない。自分は何のためにやっているんだろうって思ってしまったんです」
若い頃はピアノに限らず、一生懸命取り組めば、ものになるだろうと楽観的に考えていた。大人のピアノは、そううまくはいかない。「ものにならないなら、一体何の意味があるのか。誰もその答えを言ってくれない」。迷える稲垣を救ったのが、1冊の本だった。
ロンドン生まれのピアニスト、ジェイムズ・ローズの『ピアノが弾けるようになる本』。ピアノの練習を再開して、憧れだったドビュッシーの「月の光」のさまざまな録音を聴き漁っていた時に知った。「ロックスター・ピアニスト」の異名を持つ彼のアルバムの、クラシックの音楽家らしからぬたたずまいと、その演奏に惹かれた。
調べてみると、壮絶な人生を送った人だということも分かった。幼い頃に教師から性的虐待を受け、心の病に倒れ、何度も生活が破綻。ピアノを弾かない時期も長かったという。「厳しい時期にピアノがあったことで、内面の自由と本当の人生を取り戻すことができたと彼はつづっている」。その言葉に励まされた。
『ピアノが弾けるようになる本』でジェイムズ・ローズは、音を出すという行為を慈しみながら、ゆっくりと時間をかけて、一つの曲を完成させるように導く。1冊で弾けるようになるのはバッハの「平均律第1番前奏曲ハ長調」だけ。わずか35小節、1小節に8つの音しか出てこないこの曲を1日2小節ずつ弾いていく。
「今の世の中は競争重視。仕事に限らず、SNSも競争でしょ。『いいね』がもらえるとか再生回数を競うことが当たり前になって、個人の発信も数値化されてしまう。生活のあらゆる局面が数値化されて、その成果に振り回される。そんな時代に、大人のピアノに限って言えば、全く成果の出ないことをやろうという訳です。その矛盾とも言える行為が、私たちにわれに返る時間をくれる」
ただ聴くのではなく、自分で弾くことで、音楽との距離は全く変わってくると稲垣は言う。「頑張って1曲弾けるようになれば、人生はすごく豊かになる。そのことをジェイムズ・ローズは伝えたいんだと思う。コスパやタイパを気にするのとは対極の、人はなぜ生きるかということにもつながるエッセンスが詰まった素晴らしい本です」。気が付けば、自ら翻訳することになった。
稲垣がピアノにまつわる本を手がけるのは2冊目。大人になってからピアノに再挑戦する悲喜こもごもをつづった2022年のエッセー『老後とピアノ』はベストセラーとなった。「正直、売れるとは全く思っていなかったんです。ニッチな話だし」。だが、感想がびっしり書き込まれた「読者カード」を見て驚いた。
「私なんてまだ若い方で、70歳、80歳、90歳…と、新しく始めた方もいた。うまくならないけど、それでも弾きたいっていう人たちが“塊”でいたんです」
大人のピアノは「日陰の存在」だと稲垣は言う。人前で披露することはなかなかなく、悩みを共有できる相手もいない。子どもに交じって発表会に臨んで、1人頭が真っ白になって立ち往生することだってある。ただ何かを習得するだけではなく、子どもの頃のようにすらすらと弾けるようにはならない現実に納得し、折り合いを付けていくプロセスでもある。「ものにならなくても一生懸命続けるってことは、何かがあるってことだと思うんです。それをみんなうまく言葉にできずにモヤモヤしていたんじゃないでしょうか」
最近では街のピアノ教室に大人向けのコースが設けられ、一生懸命練習したであろう中高年がストリートピアノに挑む光景も見かけるようになった。稲垣の訳した『ピアノが弾けるようになる本』も4回増刷し好評だ。読者の半数超は50歳以上だが、30代から40代の働き盛りも3分の1程度いるという。
大人のピアノが市民権を得つつある。そのこと自体が、加速し続ける現代社会へのはかなくも、根源的な抵抗と言えるのかもしれない。(取材・文 共同通信=森原龍介)
(ジェイムズ・ローズ著、稲垣えみ子訳『ピアノが弾けるようになる本』はマガジンハウス刊・1430円)
× ×
「クレッシェンド!」は、若手実力派ピアニストが次々と登場して活気づく日本のクラシック音楽界を中心に、ピアノの魅力を伝える共同通信の特集企画です。